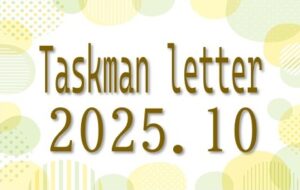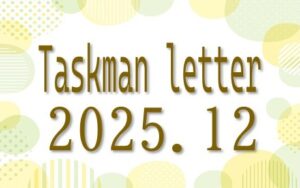2025年11月号
カスハラの法制化
カスタマーハラスメント(カスハラ)が法制化されました(改正労働施策総合推進法、令和8年施行予定)。法令上、カスハラとは「顧客等の言動であって、業務の性質その他の事情に照らし、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること」と定義されています。具体的には、次のような行為が該当します。
カスハラの典型例
①提供側に明確な落ち度がない場合の苦情
②威圧的な言動
③精神的攻撃
④継続的・執拗な行為
⑤企業側の落ち度をはるかに超える金銭補償・商品交換・サービスのやり直し・謝罪要求
介護や障害福祉の現場でも、一部の利用者によるカスハラが原因で離職に至る事例が報道されています。経営者の皆さまにおかれましては、この機会にカスハラをはじめとする各種ハラスメントの法制化について理解を深め、体制整備を検討されることをお勧めします。当社でも、制度運用に関する支援体制の構築を検討しています。
改正法にはカスハラ行為者に対する罰則規定は設けられていませんが、三重県では独自条例により「50万円以下の罰金」を科すことを検討しています。条例が成立すれば、今後、他の都道府県にも同様の動きが広がる可能性があります。
退職代行 法令違反疑い
退職代行サービス「モームリ」を運営する東京・品川区の会社「アルバトロス」が、弁護士法違反の疑いで警視庁の捜索を受けました。同社は、退職時に企業側との交渉が必要な依頼者を弁護士に紹介し、その見返りとして弁護士から違法な紹介料を受け取っていた疑いがあります。
弁護士資格を持たない者が報酬目的で弁護士業務をあっせんすることは弁護士法で禁じられています。
弁護士法 第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「退職代行」という名目のもとで行われた法律違反の可能性を示す今回の報道は、業界全体に一石を投じるものと言えるでしょう。
年末調整のご案内
各担当者より、年末調整に関するご案内を行う時期になりました。年末調整業務をご契約の場合、11月13日(木)タスクマン必着にて、ご提出をお願い致します。
年末調整は多人数の方の手続きを同時並行で行う必要があります。上記期限までにご提出いただけない場合は、当社での年末調整作業ができず、ご自身で確定申告をして頂くことになりますのでご注意ください。
なお「令和7年分年末調整申告書」は、年末調整をなされない方(ご自身で確定申告される方)も、皆様ご提出をお願い致します。
障害者グループホーム総量規制
障害者グループホーム(共同生活援助)への総量規制導入が議論されています。総量規制とは、都道府県(市町村)が計画上の必要量を超える場合に新規指定を制限できる仕組みで、事業者選定の適正化を図るものです。
背景には、営利目的の民間参入が増え、サービスの質の低下が懸念されている現状があります。食費を不正に流用した事業所「恵」事件もその象徴です。インターネット上では障害者グループホームの運営が「もうかる福祉事業」として注目され、投資対象として宣伝されるようになっています。
量の拡大から質の確保へ、障害者福祉は転換期を迎えています。
老人ホームとケアマネの関係性規制
住宅型有料老人ホームによる「囲い込み」の是正に向け、自治体が実態を把握しやすくする仕組みの整備が進められています。具体的には、ホームがケアマネ事業所や介護サービス事業所と提携する場合、提携内容を事前に行政へ報告・公表するよう求め、運営の健全性や透明性を高める仕組みを整えます。
同時に「囲い込み」防止策として、入居契約時に以下を禁止する方針を示しています。
ホーム利用にあたっての禁止事項(案)
・特定のケアマネ事業所、介護サービス事業所の利用を条件とすること
・ケアマネの変更を強要すること
・家賃優遇などで入居を誘導すること
パブリックコメントを経て最終報告書をまとめ、制度改正に向けた具体的な検討を進めていく予定です。
就労継続支援A型B型への規制
就労継続支援事業の質を高めるための「ガイドライン(案)」が示されました。今後の新規指定時、運営指導時に以下の確認が強化される可能性が高いと言えます。
今後確認が強化される事項
・必要な知識や支援力を備えているか
・安定した生産活動を行えるか
・地域ニーズを把握しているか
・なぜ就労継続支援を行うのか
・どのように利用者を募集するか
特に、生産活動の審査についての強化が予測されます。厚労省は今後、このガイドラインに基づく全国的な運用を進め、形式的な指定・指導から実質的な審査へと転換を図る方針です。
編集後記

本年8月から、毎月月末に社内研修を実施しています。当社の取り扱い業務の中から毎月1テーマを取り上げ、約75分間、講義とディスカッションを織り交ぜて進めています。
当社の良いところでもあり、悪いところでもあるのですが、研修内容の企画・資料作成・講師、すべて私担当です(涙)。1回の資料作成に毎月5~6時間ほどかかりますが、言い出しっぺなので途中で投げ出さず、継続する覚悟です。
社内研修を始めた理由は、①新人教育を担当してくれているリーダークラスの負担を軽減すること、②代表である私自身が研修を通じて職員との対話時間を増やすこと、の2点です。②についてはすでに効果を実感していますが、①の効果が現れるまでには、もう少し時間がかかりそうです。
「希望者のみ参加」という形で始めましたが、ありがたいことに参加希望者が多数に上りました。研修ルームの広さの都合で全員が一度に集まれないため、1テーマにつき毎月3日間に分けて実施しています。(これは完全に想定外です....)
この社内研修に力を注ぐことが、社員一人ひとりのスキルアップにつながり、ひいてはお客様の満足度向上につながるとの確信をもって、研修準備に励んでいます。