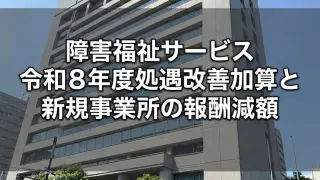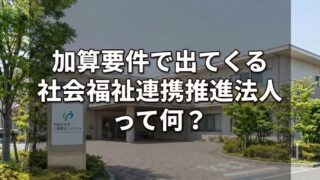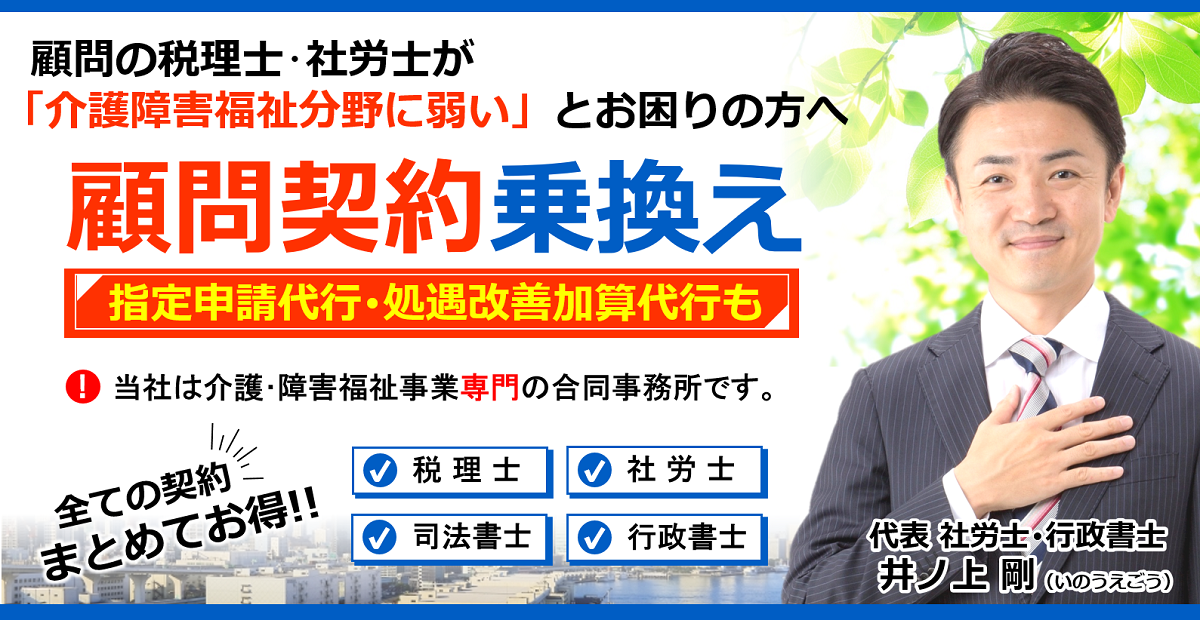【令和7年度】処遇改善加算&介護人材確保・職場環境改善等事業補助金|処遇改善加算と補助金申請を分かりやすく解説!

-1.jpg)
-1.jpg)
タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。令和7年度処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業補助金をどのサイトよりも詳しく、かつ初心者にも分かりやすく解説します。処遇改善加算制度の基礎知識、加算額の計算と分配、月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件に加えて、補助金申請まで一気にどうぞ!
このコラム推奨対象者
・処遇改善加算の基礎知識を整理したい方
・月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件をマスターしたい方
・介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の制度を理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数77名、累積顧客数は北海道から沖縄まで835社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは令和7年度処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業補助金について詳しく解説します。
- 1. 処遇改善加算の基礎知識
- 1.1. 処遇改善加算 制度の変遷
- 1.2. 加算率と加算額の計算
- 1.3. 処遇改善加算の分配ルール
- 1.4. 計画書と実績報告書の提出期限
- 1.5. 加算区分ごとの適用要件
- 2. 月額賃金改善要件
- 2.1. 月額賃金改善要件Ⅰ
- 2.2. 月額賃金改善要件Ⅱ
- 3. キャリアパス要件
- 3.1. キャリアパス要件Ⅰ
- 3.2. キャリアパス要件Ⅲ
- 3.3. キャリアパス要件Ⅱ
- 3.4. キャリアパス要件Ⅳ
- 3.5. キャリアパス要件Ⅴ
- 4. 職場環境等要件
- 5. 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金
- 5.1. 補助金の交付要件
- 5.2. 補助金の使い道
- 5.3. 補助金の申請方法と期限
- 6. まとめ
同じ内容を全5回の動画でも詳しく解説しています。
処遇改善加算の基礎知識
処遇改善加算 制度の変遷
初めに処遇改善加算制度の変遷について解説します。平成24年に創設された処遇改善加算は、令和元年、経験技能ある介護福祉職員に重点分配する特定処遇改善加算、令和4年、月給段階の賃金改善を目的としたベースアップ等支援加算を加え、複雑な3階建て構造となりました。


この複雑さを解消することを目的に、令和6年度に3制度が一本化され今日に至ります。令和7年度の処遇改善加算においては、令和6年度に実施が猶予されていた要件を理解しつつ、事業所としての対処方針を定める必要があります。以下、令和7年度処遇改善加算制度について基礎知識から詳しく見ていきます。
加算率と加算額の計算
ここでは処遇改善加算率と給付される加算額の考え方について解説します。処遇改善加算は1カ月ごとの介護報酬、障害福祉サービス報酬に加算率を掛けて計算します。つまり毎月固定的な加算額が入金されるわけではない、ということです。
加算率はサービス種別毎に、加算ⅠからⅣまで設定されています。例えば要介護者に対する訪問介護では、処遇改善加算Ⅰで24.5%、Ⅱで22.4%、Ⅲで18.2%、Ⅳで14.5%となります。


また障害者に対する居宅介護では、処遇改善加算Ⅰで41.7%、Ⅱで40.2%、Ⅲで34.7%、Ⅳで27.3%となります。サービス提供時の介護福祉職員の業務負荷に応じて、処遇改善加算率に差が設けられているわけです。
具体的な金額で例示すると、1カ月100万円に相当するサービス提供を行った場合、訪問介護の処遇改善加算Ⅰでは245,000円、居宅介護の処遇改善加算Ⅰでは417,000円もの加算が生じます。現在の処遇改善加算制度が、事業所運営上いかに大きなインパクトを持つものであるかがお分かり頂けるかと思います。
処遇改善加算の分配ルール
続いて処遇改善加算の分配ルールについて解説します。給付される処遇改善加算は、介護福祉職員の賃金改善のために使い切る必要があります。ここで2つの重要ポイントがあるため深掘りしておきます。
1点目は使い切る期限の問題です。処遇改善加算は毎月の介護報酬、障害福祉サービス報酬と同時に給付されますが、毎月給付を超える分配を行う必要はなく、その分配期限は4月から3月の1年度で区切られます。つまり毎年4月サービス提供分から翌年3月サービス提供分までの処遇改善加算の総額を計算し、それを上回る分配を行っていれば良いということです。
また、処遇改善加算は介護報酬、障害福祉サービス報酬同様に、サービス提供月から2カ月遅れで入金されるため、例えば分配期間を6月から5月と設定することも認められています。


2点目は分配対象賃金の問題です。処遇改善加算は給与明細や賞与明細での項目名を問わず、賃金改善を目的に分配するのが原則となります。従って時間外手当や通勤交通費を対象にすることはできません。


一方で、仮に処遇改善加算の分配前、年収400万円の職員に100万円の処遇改善加算を分配し、年収が500万円になると年収が増加した分、会社が負担する社会保険料が増大します。


会社が負担する社会保険料は賃金の概ね15%に相当するため、このケースでは100万円×15%、つまり1人あたり年間15万円もの社会保険料が増加する計算となります。職員数が多い場合、大変な負担額となります。
そこで分配方法唯一の例外として「処遇改善加算を会社負担社会保険料の増額分に充当して良い」とされています。先ほどの例で言うと、ある職員に100万円分の処遇改善加算を分配予定である場合、給与と賞与の合計で年間87万円の処遇改善加算を分配し、87万円×15%、つまり社会保険料増額分13万円を処遇改善加算から充当するという考え方です。


結果的にこの職員に対して100万円の賃金改善を行ったことになります。
以上2点が処遇改善加算を考える上での最重要ポイントです。
計画書と実績報告書の提出期限
続いて、処遇改善加算の計画書と実績報告書の提出期限について解説します。処遇改善加算の適用を受けたい場合、年度ごとに計画書を提出し、年度終了ごとに実績報告書を提出する必要があります。
初めて処遇改善加算の適用を受ける場合、対象月の前々月末が計画書の提出期限です。例えば、8月から処遇改善加算の適用を受けたい場合、6月30日が計画書の提出期限となります。
年度初めは厚生労働省からの新様式の公表時期の問題から、4月または5月から処遇改善加算の適用を受ける場合、計画書の提出期限は例年4月15日となります。
実績報告書の提出期限は最終の処遇改善加算の入金月から2か月後の末日です。通常営業している場合、3月分の処遇改善加算が5月に入金されるため、実績報告書の提出期限は7月31日となります。
いずれも各都道府県や市によって個別の期限を設ける場合がある点にご注意下さい。
加算区分ごとの適用要件
続いて、処遇改善加算区分ごとの適用要件の全体像を解説します。令和7年度の処遇改善加算区分はⅠからⅣに分かれます。合計8項目の要件が定められており、加算Ⅰの適用要件が最も厳しくなります。


具体的には加算Ⅰでは8項目の全てを満たす必要があり、加算Ⅱではキャリアパス要件Ⅴ以外を、加算Ⅲではキャリアパス要件ⅣとⅤ以外を、加算Ⅳではキャリアパス要件Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ以外を満たす必要があります。
月額賃金改善要件
月額賃金改善要件Ⅰ
ここでは月額賃金改善要件Ⅰについて解説します。月額賃金改善要件Ⅰは処遇改善加算ⅠからⅣの全てに共通して適用されます。月額賃金改善要件Ⅰの趣旨としては・・・


処遇改善加算を職員に分配する際は、一定額以上を毎月の固定額として支払ってくださいね。
という内容になります。処遇改善加算が一本化された令和6年度より前は、賞与や一時金など、変動的な方法による事業所が多かったことに対する是正であると言えます。
ここで言う「一定額」について詳しく見ていきます。ある訪問介護事業所の処遇改善加算を除く介護報酬の1年間の総額が2000万円であるとします。


この事業所が処遇改善加算ⅠからⅣのいずれを算定している場合であっても、仮にⅣを算定したと仮定し、その処遇改善加算額を計算します。訪問介護の場合、処遇改善加算Ⅳの加算率は14.5%であるため、2000万円×14.5%で290万円となります。この290万円の2分の1、つまり145万円が先ほど解説した「一定額」です。
この事業所では年間145万円以上は賞与や一時金ではなく、毎月の固定額として職員へ分配、つまりベースアップを行う必要がある。これが月額賃金改善要件Ⅰの考え方です。
この事業所が実際に処遇改善加算Ⅰを算定する場合、処遇改善加算総額は2000万円×24.5%で490万円になるため、490万円のうち145万円を毎月の固定額として職員へ分配する必要があるということになります。事業所が処遇改善加算Ⅱ、Ⅲを算定する場合であっても同様の考え方です。
このように月額賃金改善要件Ⅰを設けることで、事業所に給付される処遇改善加算のうち、一定額以上が毎月確実に職員に分配されるよう、ベースアップのルールを設けているわけです。
一方で、月額賃金改善要件Ⅰには緩和措置が講じられています。具体的にはこの月額賃金改善要件Ⅰを満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はないという内容です。
具体的数値を用いて解説します。この事業所では、賞与での分配比率が高く、毎月の給与で100万円、賞与で390万円を分配しているとします。


この時点で毎月分配すべき145万円に45万円足りません。この場合、賞与を45万円減額して345万円とし、その45万円を毎月の給与に付け替えて145万円にすることで要件を満たすことができます。
月額賃金改善要件Ⅱ
続いて、月額賃金改善要件Ⅱについて解説します。月額賃金改善要件Ⅱは処遇改善加算ⅠからⅣの全てに共通して適用されますが、適用対象となる事業所は限定的なものとなります。具体的には、処遇改善加算が一本化された令和6年6月1日の前日段階で、旧処遇改善加算を算定しつつも旧ベースアップ等支援加算を算定していなかった事業所に限られます。


月額賃金改善要件Ⅱの趣旨としては・・・


ベースアップ等支援加算を算定する機会があったにも関わらず、あえて算定しなかった事業所と、ベースアップ等支援加算を算定したことで基本給のベースアップを実施した事業所の不均衡を是正しますよ。
という内容となります。具体的に見ていきます。
旧ベースアップ等支援加算では、給付される加算額の3分の2以上の額を基本給など毎月の固定額をベースアップする必要があり、事業所はこの要件に応じてベースアップを実施したわけです。


令和6年6月1日の処遇改善加算一本化後は、処遇改善加算ⅠからⅣの全てに旧ベースアップ等支援加算率を引継いだため、旧ベースアップ等支援加算を算定せず令和6年6月1日を迎えた事業所は、処遇改善加算Ⅰ~Ⅳには該当せず、臨時的に設けられた処遇改善加算Ⅴに移行しました。
このような事業所が令和7年度に処遇改善加算ⅠからⅣのいずれかの適用を受ける場合、旧ベースアップ等支援加算相当額の3分の2以上のベースアップを行う必要がある。これが月額賃金改善要件Ⅱの考え方です。 月額賃金改善要件Ⅱの適用を受ける場合、計算式が非常に複雑になるため、計画書および実績報告書いずれでも、旧ベースアップ等支援加算相当額が自動計算されるよう配慮がなされています。
キャリアパス要件
ここでは、キャリアパス要件の全体像について解説します。キャリアパス要件では、処遇改善加算Ⅰ~Ⅳと同じローマ数字が用いられているため、誤解のないようにご注意下さい。
処遇改善加算Ⅰ~Ⅳとキャリアパス要件Ⅰ~Ⅴの対応関係を図示すると次のようになります。


図の通り、処遇改善加算Ⅰではキャリアパス要件Ⅰ~Ⅴのすべてを満たす必要があり、処遇改善加算ⅡではⅠ~Ⅳを、処遇改善加算ⅢではⅠ~Ⅲを、処遇改善加算ⅣではⅠとⅡを満たす必要があります。キャリアパス要件ⅣとⅤは、旧特定処遇改善加算の要件を引き継いでいます。
キャリアパス要件Ⅰ
初めに、キャリアパス要件Ⅰについて解説します。キャリアパス要件Ⅰは処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの全てに共通して適用される要件です。キャリアパス要件Ⅰの趣旨としては・・・


介護福祉職員を雇用するからには、就業規則に役職と賃金を記載し、職員に公開して経営に透明性を持たせてくださいね。
という内容になります。具体的には役職名・役職ごとの責任・仕事内容を明らかにした、キャリアパス表と、それに対応する賃金体系図を就業規則に記載して職員に公開します。


厚生労働省の例ではキャリアパス表と賃金体系図が一体化されていますが、将来賃金体系を細かく階層化したい場合は、給与部分を賃金体系図として分離作成した方が良いでしょう。


ただし、令和6年度同様に令和7年度においても、令和8年3月31日までの実施を誓約することで、この要件を満たすとする猶予措置が講じられています。
キャリアパス要件Ⅲ
順番が前後しますが、キャリアパス要件Ⅰと関連性の深いⅢについて解説します。キャリアパス要件Ⅲは処遇改善加算Ⅰ~Ⅲに求められる要件です。
キャリアパス要件Ⅲの趣旨としては・・・


どのように努力すれば賃金が上がるのか、昇給ルールを就業規則に記載し職員に公開して経営に透明性を持たせてくださいね。
という内容になります。もう少し分かりやすく具体例を用いて解説します。
ある職員がキャリアパス表で言う初級職で入社して1年が経過したとします。この段階では未だに中級職に求められる任用要件には、条件的に届かず初級職に留まっています。


このように、同じ職位に留まる場合でも、定期的な査定により昇給する機会を作り就業規則への記載を求めるのがキャリアパス要件Ⅲです。
キャリアパス要件Ⅲで求められる昇給の機会については3種類あり、事業所は少なくとも1つ以上を選択する必要があります。


1点目は「年数」に着目した昇給です。自社での勤務年数や、介護福祉職員としての経験年数に応じて毎年定期昇給する方法です。
2点目は「保有資格」に着目した昇給です。例えば介護福祉士資格を保有していれば3万円、実務者研修修了段階であれば1万円など、資格手当を設ける方法です。
3点目はいわゆる「能力評価」です。1点目、2点目のような形式的な要素とは異なり、職員個々の能力評価を行い、昇給する方法です。
当社の経験則としては、これら3種類の組み合わせにより、キャリアパス要件Ⅲを満たす事業所が多いように感じます。例えば毎年4月に、少額ではあるけれども定期昇給し、保有資格や能力評価によって充分な昇給を実現する。そしてこれらの昇給は事業所に給付される処遇改善加算額により行う、と言った内容です。昇給のウエイトとしては3点目の「能力評価」を重視する事業所が多いようです。
ここで解説したキャリアパス表、賃金体系図に加えて、能力評価を行う場合の人事評価シートについても当社のサポートの中でお客様にご提供しています。
なお、キャリアパス要件Ⅲについても、令和8年3月31日までの実施を誓約することで、令和7年4月1日からこの要件を満たすとする猶予措置が講じられています。
キャリアパス要件Ⅱ
続いて、キャリアパス要件Ⅱについて解説します。キャリアパス要件Ⅱは処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの全てに共通して適用される要件です。キャリアパス要件Ⅱの趣旨としては・・・


職員のスキルアップのために、事業所は具体的な支援計画を策定し、職員に公開した上で実施して下さいね。
という内容になります。ここで言う「具体的な支援計画」については大きく分けて2種類あり、事業所は少なくともどちらか一方を選択する必要があります。


1点目は事業所が主体となって行う研修、2点目は職員が自主的に取り組む資格取得への援助です。援助の内容としては通学のための勤務シフト調整、休暇付与、費用負担などが該当します。これらは事業所が独自の判断で詳細を決定することができます。
なお、キャリアパス要件Ⅱについても、令和8年3月31日までの実施を誓約することで、令和7年4月1日からこの要件を満たすとする猶予措置が講じられています。
キャリアパス要件Ⅳ
続いて、キャリアパス要件Ⅳについて解説します。キャリアパス要件Ⅳは処遇改善加算ⅠとⅡに適用される要件です。キャリアパス要件Ⅳの趣旨としては・・・


処遇改善加算ⅠとⅡは、旧特定処遇改善加算を引き継いでいるため、経験技能ある職員のうち1人以上は年収440万円以上にして下さいね。
という内容になります。この趣旨を正しく理解するためには、令和6年5月31日まで存在した、旧特定処遇改善加算制度を理解する必要がありますが、すでに廃止された制度のため簡単に触れるに留めます。
平成24年にスタートした旧処遇改善加算制度の下で、令和元年に特定処遇改善加算が加わりました。厚生労働省が「介護福祉士」を介護福祉業界のキャリア目標として明確化したいとの方針が、その背景にあります。


そのため、特定処遇改善加算の分配対象は「10年以上キャリアのある介護福祉士」がモデルとされました。その際に設けられた要件が、「加算額の分配の結果、1人以上は年収440万円以上にする」というものです。これが3制度一本化後のキャリアパス要件Ⅳとして引き継がれているわけです。
キャリアパス要件Ⅳの年収440万円基準を考える上で、2つのポイントがあるため深掘りして解説を続けます。
1点目は、年収の判定基準です。ここで言う「年収440万円以上の職員」とは、処遇改善加算の分配の結果、年収440万円以上となる職員を指します。従って処遇改善加算の分配前から年収が440万円以上である職員は該当しない点に注意が必要です。
2点目は、どうしても年収440万円以上の職員を生むことができない場合の救済措置です。処遇改善加算は介護報酬または障害福祉サービス報酬に加算率を掛けて給付されるため、土台となる介護報酬または障害福祉サービス報酬が少額である場合には加算額も連動して少額となり、結果的に職員への分配額も少額となります。このようなケースでは、事業所がどのように努力しても、職員の年収を440万円以上とすることは困難です。


そこで、令和7年度の処遇改善加算計画書および実績報告書では、「年収440万円以上の職員を生むことができない理由」を記す欄が予め設けられています。よくある事例にチェックマークを入れるだけで済む配慮がなされているため、小規模事業所にとっても事務処理は比較的容易かと思います。
キャリアパス要件Ⅴ
続いて、キャリアパス要件Ⅴについて解説します。キャリアパス要件Ⅴは別名「介護福祉士等の配置要件」とも呼ばれ、処遇改善加算Ⅰに限って適用されます。キャリアパス要件Ⅴの趣旨としては・・・


処遇改善加算Ⅰでは、旧特定処遇改善加算Ⅰを引き継いでいるため、別に定める体制加算を取って下さいね。
という内容になります。旧特定処遇改善加算はⅠとⅡに分かれており、Ⅰに求められた介護福祉士等の配置要件が現行制度のキャリアパス要件Ⅴとして引き継がれているわけです。具体的に見ていきます。
ここで言う「別に定める体制加算」については、サービス種類によって異なります。具体的には訪問介護や障害者向け居宅介護・重度訪問介護等では特定事業所加算ⅠまたはⅡ、通所介護ではサービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡ、居宅介護・重度訪問介護以外の障害福祉サービスでは福祉専門職員配置等加算が該当します。


いずれの加算も事業所に一定数以上の専門職員が配置されていることを条件とする加算です。このような加算を算定することが、処遇改善加算Ⅰに求められるキャリアパス要件Ⅴに繋がるわけです。
職場環境等要件
ここでは、職場環境等要件について解説します。職場環境等要件は処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの全てに適用されますが、加算率の高い処遇改善加算ⅠとⅡには厳しい要件が適用されます。


職場環境等要件の趣旨としては・・・


働きやすい職場環境の改善に努めて下さいね。
という内容になります。具体的に見ていきます。
職場環境等要件は6つのカテゴリーにまとめられています。具体的には「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」、以上6カテゴリー、合計28の実施項目が示されています。


処遇改善加算ⅠとⅡでは、各カテゴリーから2つ以上選択し、かつ生産性向上のカテゴリーに限り3つ以上選択した上で、取組み内容をホームページなどで公表する必要があります。処遇改善加算ⅢとⅣでは各カテゴリーから1つ以上選択し、かつ生産性向上のカテゴリーに限り2つ以上選択する必要があります。
生産性向上の8項目に力点が置かれているため、内容を概観しておきましょう。
生産性向上の8項目
⑰厚生労働省が示す「生産性向上ガイドライン」に基づく業務改善活動の体制構築 (委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。居宅サービスにおいてはケアプラン連携標準仕様を実装しているものに限る)及び情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)については、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICT、インフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
⑰⑱のいずれかについて、処遇改善加算ⅠとⅡでは選択必須項目となります。
一方で「生産性向上のための業務改善の取組」には特例的措置が2点設けられているため、少し触れておきたいと思います。
1点目は居住系の介護施設等での「生産性向上推進体制加算」の取得です。「生産性向上推進体制加算」を取得していれば、「生産性向上のための業務改善の取組」の要件を満たすものとして取り扱われます。「生産性向上推進体制加算」では見守り機器・インカム等のICT機器導入が求められるためです。
2点目は小規模事業所での㉔の取組実施です。この場合も「生産性向上のための業務改善の取組」の要件を満たすものとして取り扱われます。
以上が職場環境等要件の全体像ですが、介護障害福祉業界からは「職場環境等要件への適応が困難である」との声が多数上がっているため、令和8年3月31日までの実施を誓約する場合、または「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」を申請する場合も、職場環境等要件への対応が猶予されます。
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金
ここでは、令和7年度処遇改善加算と連動して実施される「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」について解説します。
「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」は令和6年度補正予算により、介護事業所・障害福祉事業所に交付されるものです。対象となる月を令和6年12月から令和7年3月の中から事業所自らが選択し、選択した月の介護報酬または障害福祉サービス報酬に、サービス種別ごとに定められる補助金交付率を掛けて補助金が交付されます。


補助金の交付率を表にまとめました。


訪問介護で10.5%、通所介護で6.4%、障害者向け居宅介護、重度訪問介護で12.7%、以下ご覧の通りです。仮に訪問介護事業所で処遇改善加算を含む1カ月の介護報酬の総額が100万円である場合、交付率10.5%を掛けて105,000円の補助金が交付されます。
補助金の交付要件
続いて、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付要件について解説します。補助金の交付要件としては大きく分けて2点あります。
1点目は処遇改善加算の算定要件です。令和6年12月から令和7年3月の中から事業所自らが選択する基準月時点で、処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを算定している必要があります。なお、仮にこの要件を満たさない場合であっても、令和7年4月15日までに、令和7年度処遇改善加算Ⅰ~Ⅳを取得する手続きを終えていれば良い、との猶予措置も講じられています。該当する事業所は早めに手続きに取り掛かることをお勧めします。
2点目は職場環境改善に向けた取り組みの実施です。
職場環境改善に向けた取り組みの実施
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
・業務改善活動の体制構築、具体的には委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等
この中から、1つ以上を選択して実施する必要があります。この取り組みを行うことにより、処遇改善加算制度側で求められる職場環境等要件への対応が令和8年3月31日まで猶予されるという特典が付いてきます。
補助金の使い道
続いて、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の使い道について解説します。補助金の使い道については、処遇改善加算の分配とは別枠で管理する必要があります。具体的には2つの方法が定められているため、詳しく見ていきます。
1点目は人件費の改善です。処遇改善加算と異なり、1回だけの補助金交付であるため、毎月の固定給与をベースアップすることには適しません。従って、人件費改善に充てる場合は、賞与など一時金支給を行う事業所が大半であると予測されます。この場合、処遇改善加算の分配とは別枠で管理する必要があるため、支給明細には「補助金対象一時金」など分かりやすい項目名を付けることをお勧めします。
2点目は職場環境改善のための経費です。厚生労働省が示す具体例としては、研修費、介護助手の募集経費のほか、処遇改善加算制度側で定める「職場環境等要件」を推進するための経費が該当します。ただし、介護テクノロジー等の機器購入費用については、別途設ける「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」により対応するため、今回の補助金から支出することはできません。
補助金の申請方法と期限
最後に、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の申請方法と期限について解説します。過去の年度でも類似の補助金制度が存在しましたが、処遇改善加算計画書とは別に補助金申請書を作成する必要があったため、事業所の事務負担の増大が問題視されていました。
令和7年度では、処遇改善加算計画書と補助金申請書の様式が一体化されたことにより、事業所の事務負担は一部軽減されます。
具体的には、事業所に関する「基本情報入力シート」が処遇改善加算と補助金で共有されるため、同じ内容を二度入力する手間を省くことができます。
ただし提出先については注意が必要です。処遇改善加算計画書の提出は事業所の指定権者である一方、補助金申請書は全て都道府県となります。


例えば政令市や中核市に位置する事業所の場合、処遇改善加算計画書は市へ提出し、補助金申請書は都道府県へ提出します。この点、間違いのないように管理する必要があります。
処遇改善加算計画書、補助金申請書の提出期限は原則、令和7年4月15日です。各都道府県や市により、個別の期限を設ける場合がある点にご注意下さい。
まとめ
今回のコラムでは、令和7年度処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業補助金をどのサイトよりも詳しく、かつ初心者にも分かりやすく解説しました。処遇改善加算制度の基礎知識、加算額の計算と分配、月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件に加えて、補助金申請の方法がご理解頂けたかと思います。
事業所の運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】