【令和6年度法改正対応】訪問介護の同一建物減算|4つの減算区分を分かりやすく解説|訪問介護の開業講座⑱

-1.jpg)
-1.jpg)
タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。訪問介護事業の開業予定者、または制度理解に不安のある経営者向けに「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第18回のテーマは「訪問介護の同一建物減算」です。同一建物減算の全体像と、令和6年度報酬改定で新たに設けられた減算区分についても詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・同一建物減算の定義と4つの減算区分を知りたい方
・同一建物減算に関して居住利用者数の判定方法、利用者割合の判定方法について知りたい方
・減算率12%区分が新たに設けられた理由について知りたい方
・減算率12%区分の適用除外(正当理由)について知りたい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数77名、累積顧客数は北海道から沖縄まで834社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは同一建物減算の全体像と、令和6年度報酬改定で新たに設けられた減算区分について詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
同一建物減算の定義
初めに、同一建物減算の定義から解説します。地域に点在する利用者住居を訪問する場合と比較して、利用者が集合住宅など同じ建物に居住する場合、訪問介護員の移動時間を削減できるため、訪問介護報酬でバランスを取るのが同一建物減算の目的です。


そのため、訪問介護事業所と建物の所有・管理運営が別法人の場合も、当然に同一建物減算は適用されます。
訪問介護事業所と同一の建物に利用者が居住する場合に、同一建物減算が適用されるのが基本型ですが、その他にも減算が適用される場合があります。2つの類型があるため、詳細を解説します。
類型① 異なる建物(距離が近接する)
類型①は訪問介護事業所と異なる建物であっても、その距離が近接するケースです。具体的には事業所と同一敷地内の別建物、事業所と隣接する敷地の建物、道路を挟んで隣接する建物などが該当します。


このようなケースでも訪問介護員の移動時間を削減できるため、同一建物減算の対象となります。
一方、たとえ同一敷地内の建物であっても、敷地が広大で訪問介護員の移動時間を削減できない大規模団地や、事業所からの直線距離は近くても、幹線道路や河川があるため迂回して訪問しなければならない場合、訪問介護員の移動時間の削減に繋がらないことから、同一建物減算の対象外となることがあります。


類型② 異なる建物(距離が近接しない)
類型②は事業所と建物の距離が近接していなくても、一つの建物に複数の利用者が居住するケースです。このケースでも、一度その建物へ訪問すれば、後は訪問介護サービスを連続して提供することができるため、同一建物減算の対象となります。


以上の通り、基本型以外にも、2つの減算対象がある点を理解しましょう。
同一建物減算 4つの減算区分
続いて、同一建物減算の4つの減算区分について解説します。減算区分を図示すると次のようになります。


ABCが訪問介護事業所と同一の建物に利用者が居住するケースです。これには先にご説明した同一敷地、隣接敷地、道路を挟み隣接するケースが含まれます。Dが事業所と建物の距離が近接していなくても、一つの建物に複数の利用者が居住するケースです。
それぞれ、訪問介護員の移動時間の削減度合いに着目し、10%、12%、15%の減算率が設定されています。Cは令和6年度報酬改定で新たに設けられた区分です。以下、具体的に解説を進めます。
居住利用者数の判定方法
まずは居住利用者数の判定方法です。Bでは50人以上、Dでは20人以上で減算が適用されるため、人数の判定方法を理解することが重要となります。
人数の判定のためには、サービス提供月における1日ごとの居住利用者数の算出から行います。ただしその月に訪問介護の提供がない利用者は除きます。1日ごとの居住利用者数を1カ月合計し、その月の暦日数で割ることで月平均を算出します。小数点以下は切り捨てます。このように計算することで、月の途中で入退居する利用者を含めて人数を判定します。


利用者割合の判定方法
続いて利用者割合の判定方法です。先に解説したABDでは居住利用者数を毎月計算し、同一建物減算の適用判定を行うのに対して、Cでは半年ごとに計算判定し、減算が適用される場合、半年間継続する点に注意が必要です。
判定は前期分として3月1日から8月31日までの計算結果を9月15日までに提出し、10月1日から3月31日に減算適用、後期分として9月1日から2月末日までの計算結果を3月15日までに提出し、4月1日から9月30日までの減算適用となります。90%以上にならない場合でも計算書類を作成し、事業所で2年間保存する義務があります。


具体的な計算方法を解説します。まずは分母からです。分母には判定期間に訪問介護を提供した全利用者の実際の人数を用います。分子には同一敷地内建物に居住する利用者の実際の人数を用います。分子からは図で言うBとDの減算適用を受ける利用者を除きます。


Bを除く理由としては、BではCの12%より高い15%の減算率が適用され、重ねて減算適用する必要がないためです。
Dを除く理由としては、Cの減算目的が、あくまでもABだけではカバーできないケースを対象にするためです。この点、減算率12%区分が新たに設けられた理由とも関連するため、次の項目で詳しく解説します。
減算率12%区分が新たに設けられた理由
ここでは、減算率12%区分が新たに設けられた理由を考えたいと思います。ABいずれの場合も、事業所と利用者居住建物は同一、または近接しています。有料老人ホームの建物内に、訪問介護事業所が置かれているようなケースです。
このケースでは50人以上で15%という高い減算率が適用されるため、事業所側には「49人までに抑えたい」との意識が働きます。
令和6年度報酬改定は、この点に配慮しつつも、「その建物への訪問介護提供を主眼に設立された事業所」つまり「その建物以外への訪問介護提供を原則行わない事業所」に対して、新たに減算を適用するのが目的です。報酬制度の不均衡を是正する報酬改定であると言えます。
減算率12%区分の適用除外(正当理由とは)
最後に、減算率12%区分の適用除外を受ける「正当理由」について解説します。先に解説した半年ごとの計算の結果、対象利用者割合が90%を超える場合であっても、指定権者が「正当理由あり」と認めた場合には、減算が適用除外されます。
「正当理由」については、事業所自らが書類を作成し、指定権者へ提出する必要があります。厚生労働省から「正当理由」の考え方について例示があるため、ご紹介しておきます。
正当理由の例示
①「特別地域訪問介護加算」の適用事業所。離島など訪問介護サービスの提供が困難な地域で運営する事業所への配慮からです。
②月間訪問回数が200回以下など、事業所が小規模である場合。計算に用いる分子・分母共に数値が小さく、利用者数の変動が計算結果に大きな影響を与えるためです。
③地域性により同一建物以外に居住する要介護者が少数である場合。同一建物以外でのサービス提供を行おうにも、対象者が少なければどうにもならないためです。
一方で「たまたまケアマネージャーから、同一建物以外の利用者の紹介がない」などの理由は「正当理由に該当しない」との見解が示されています。
まとめ
「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」、第18回は「訪問介護の同一建物減算」を解説しました。同一建物減算の全体像と、令和6年度報酬改定で新たに設けられた減算区分についてご理解頂けたかと思います。
会社設立・運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538

の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー.png)
-320x180.jpg)
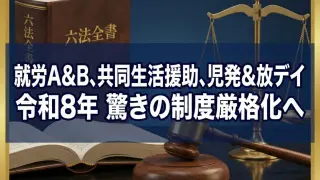

|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)

様-02-300x243.png)
