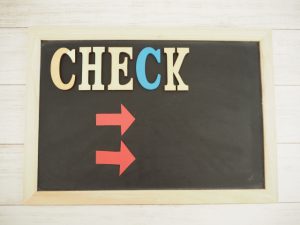処遇改善加算とは?【計画届・実績報告】の仕組みを網羅。最新の処遇改善加算制度をどのサイトよりも分かりやすく解説!

-1.jpg)
-1.jpg)
介護職員処遇改善加算とは?年間手続きは?給付率は?処遇改善加算に関する初歩的な疑問から、専門的な課題まで完全網羅します。このコラムを読むと、あなたも処遇改善加算の全体像が理解できるはずです。しかも10分で読めます。処遇改善加算の対象業種の場合、算定はマストです。介護障害福祉労働者のためにも、是非取り組んでください。
このコラムの推奨対象者
・処遇改善加算の全体像を理解したい人
・処遇改善加算の業種別の加算額(率)を理解したい人
・処遇改善加算を取るための手続きの流れを理解したい人
このコラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に特化した、専門会社です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年7月時点、介護障害福祉事業の累積設立支援件数が400社を越えました。処遇改善加算についても全職員が専門的知識に基づいて対応していますので、安心してお読み下さい。
- 1. 処遇改善加算とは?処遇改善加算を一言で説明
- 2. 処遇改善加算の金額は?業種別の算定方法
- 2.1. 介護職員処遇改善加算の業種別の給付掛け率
- 2.2. 具体的事例
- 3. 処遇改善加算の支給対象職種は?
- 4. 処遇改善加算を受けるための手続きは?計画届と実績報告
- 4.1. 1.処遇改善加算は毎年度、手続きが必要
- 4.2. 2.年度の途中で処遇改善加算を受けることはできないのか?
- 4.3. 3.開業初年度(指定と同時)は処遇改善加算を受けることはできるのか?
- 5. 処遇改善加算計画届作成上の注意点、ポイントは?
- 5.1. ポイント1.「受取額<配分額」
- 5.2. ポイント2.「実施期間」
- 5.3. ポイント3.「加算のレベル」
- 5.4. 処遇改善加算1~3の要件
- 6. 処遇改善加算実績報告書作成上の注意点、ポイントは?
- 7. 処遇改善加算のサポートは社会保険労務士の専門分野
・
処遇改善加算とは?処遇改善加算を一言で説明
「介護職員処遇改善加算」
介護業界のことを知らない人でも、介護保険の報酬算定方法を知らない人でも理解できるように、一言で処遇改善加算を説明します。
介護職員処遇改善加算を一言で言うと・・・
ヘルパーさんが働きやすい環境をつくる介護・障害福祉事業所に対して、国が特別の給付を行うので、給付額を超える金額をヘルパーさんに還元してくださいね。
という仕組みです。初めて処遇改善加算に触れる人には、きっと次の疑問が出てくるでしょう。
処遇改善加算 よくある疑問点
「ヘルパーさんが働きやすい環境って何?」
「国がくれる給付ってどれくらいの金額?」
「給付額を超える金額をヘルパーさんに還元するってどういうこと?」
「処遇改善加算を受けるための手続きは?」
このコラムではこれらの初歩的な疑問に答えるとともに、すでに介護・障害福祉事業所で管理者や責任者をしているような方々にも、より深く処遇改善加算を理解してもらえるように配慮して執筆しました。
このコラムをお読みいただいた後は、是非「特定処遇改善加算」についてのコラムも併せてお読み下さい。もう1つ上のステップでの理解が深まるはずです。
処遇改善加算の金額は?業種別の算定方法
ここでは介護職員処遇改善加算の「実際の給付金額」について解説します。まずは基本的知識から。処遇改善加算は固定金額ではなく、給付掛け率(パーセント)を用いて計算した金額が給付されます。具体的な算定方法次の通りです。
処遇改善加算の計算方法
( 基本報酬 + 加算報酬 - 減算報酬 )×業種別の給付掛け率
「基本報酬」の部分が大半を占めるため、このコラムでは加算報酬、減算報酬の説明は省略します。
介護職員処遇改善加算の業種別の給付掛け率
| 指定業種 | 加算1 | 加算2 | 加算3 |
| 訪問介護 | 13.7 | 10 | 5.5 |
| 通所介護 | 5.9 | 4.3 | 2.3 |
| 居宅介護(障害) | 27.4 | 20.0 | 11.1 |
| 重度訪問介護(障害) | 20.0 | 14.6 | 8.1 |
| 同行援護(障害) | 27.4 | 20.0 | 11.1 |
| 行動援護(障害) | 23.9 | 17.5 | 9.7 |
| 就労移行支援 | 6.4 | 4.7 | 2.6 |
| 就労継続支援A型 | 5.7 | 4.1 | 2.3 |
| 就労継続支援B型 | 5.4 | 4.0 | 2.2 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 8.6 | 6.3 | 3.5 |
| 放課後等デイサービス | 8.4 | 6.1 | 3.4 |
| 児童発達支援 | 8.1 | 5.9 | 3.3 |
数値は%(パーセント)。加算1~3の違いについてはコラムの後半で説明します。
具体的事例
具体的事例を用いて説明します。
30分の訪問介護を利用した場合、訪問介護事業者は396単位の介護報酬を得ることができます。ここに処遇改善加算1の給付掛け率を乗じると、396×13.7%=54単位。結果として次の介護報酬を請求することができます。
396(元の訪問介護報酬)+54(処遇改善)=450単位
1単位10円で計算すると、4500円となります。処遇改善加算部分は540円です。なお、処遇改善加算を受けることで、利用者側の負担もそれに応じて増加する点に注意が必要です。介護事業所の人件費の一部を、利用者も負担しているわけです。1割負担者の場合、約54円負担が増えることになります。
処遇改善加算の支給対象職種は?
続いて介護職員処遇改善加算の「支給対象職種」を確認しましょう。
処遇改善加算は、あくまでも「現業」つまり要介護者、障害者、障害児に対して、「実際のケアを行う職種」の処遇を改善することが目的です。そのため支給対象は、主に次の職種と定められています。
処遇改善加算の主な支給対象職種
・介護職員(訪問介護、通所介護、障害居宅介護、障害重度訪問介護など)
・生活支援員、世話人(共同生活援助など)
・職業指導員、就労支援員(就労移行支援、就労継続支援など)
・児童指導員(放課後等デイサービス、児童発達支援など)
一方、主に次の職種は支給対象外となります。
処遇改善加算の支給対象「外」職種
・法人代表者、役員
・管理者
・サービス提供責任者(介護職員を兼ねる場合は○)
・看護師
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・生活相談員
・サービス管理責任者
・児童発達管理責任者
ただし、これらの「支給対象外職種」の人が、「支給対象職種」を兼務し、かつ勤務体制一覧(シフト表)で勤務時間が確保されている場合は、その勤務部分に関して処遇改善加算の支給が可能となる、とされています。この点については、自治体によって若干の判断差異があるので個別確認をお勧めします。
処遇改善加算を受けるための手続きは?計画届と実績報告
ここでは介護・障害福祉事業所が介護職員処遇改善加算を受けるための具体的な手続きについてご説明します。処遇改善加算が、他の加算と大きく異なるのは、「毎年度、計画届と実績報告書の提出が必要」となる点です。具体的事例を挙げます。
1.処遇改善加算は毎年度、手続きが必要
介護・障害福祉分野では4月1日~3月31日を1年度として定めています。ここで言う年度は、事業所(法人)の決算年度とは何の関係もありません。
年度初め(4月)から処遇改善加算を受けたい事業所は、2月末までに計画届を提出しなければなりません。この点は多くの自治体での共通ルールです。
そして実績報告を年度終了後(3月31日)から4カ月以内(7月31日)に提出します。これを毎年繰り返す必要があります。
2.年度の途中で処遇改善加算を受けることはできないのか?
それでは2月末までに処遇改善加算計画届を提出しなかった場合、その年度は処遇改善加算を受けることはできないのでしょうか?そのようなことはないのでご安心を。
年度の途中から処遇改善加算を受けたい場合は、受けたい月の「前々月末」までに計画届を提出すればOKです。
3.開業初年度(指定と同時)は処遇改善加算を受けることはできるのか?
「開業(指定)と同時に処遇改善加算を受けることはできますか?」
との質問をよく受けますが、問題なく可能です。指定申請書の提出に合わせて処遇改善加算の計画届を提出すれば、開業(指定)と同時に処遇改善加算を受けることができます。
処遇改善加算計画届作成上の注意点、ポイントは?
ここでは介護職員処遇改善加算の「計画届」作成上のポイントを解説します。実際の届出書は自治体ごとに若干の差がありますが、次の3点さえ理解していれば、どのような自治体の計画届でも対応できるので、是非習得頂きたいと思います。
ポイント1.「受取額<配分額」
これは処遇改善加算の根幹をなす考え方です。国から支給される処遇改善加算額を、「1円でも上回る額」を対象職種の従業員に支給しなければならない、ということです。
例えば、年度で1,000,000円の処遇改善加算を受ける見込みの場合、少なくとも1,000,001円を対象職種の従業員に支給する必要があります。
計画届では、あくまでも「受取見込額 < 配分見込額 を実現できる」との予測数値を示すだけでOKです。配分は月々の給与であっても、ボーナスなどの一時金であっても構いませんが、国の方針は「なるべく基本給のアップを」となっています。
さらに言うと「配分見込額」には、次の金額を含めることが認められています。
処遇改善加算の配分額に含めることができる金額
対象従業員に処遇改善加算を支給することで増額する、事業主負担の社会保険料
例えば、処遇改善加算の支給により、月給が2万円上がることで、社会保険等級が上昇。その差額部分を「処遇改善加算の配分」とみなすことが出来るわけです。
ポイント2.「実施期間」
次に重要なのが、ポイント1で示した計画を、いつまでに実施する予定か、という点です。つまり対象職種の従業員に、処遇改善加算を支給し終わる期限のことです。
処遇改善加算が年度(4~3月)を基準に、毎月国から支給されるということは説明しました。これを受けて、実施期間(支給期限)も年度で区切らなければならないのは当然のことです。
しかし、処遇改善加算を含む介護報酬が、サービス提供月から「2カ月遅れで入金される」という点、および「実績報告書の提出期限が7月31日である」点を理由に、多くの自治体では、5月末または6月末までを、実施の期限として認めています。
まとめると次のようになります。
処遇改善加算の配分 実施期間の考え方
・毎年度4月~3月にサービス提供する部分に対して、処遇改善加算を受け取る
・実際の入金は2カ月遅れとなるため、実際の受け取りは6月~5月
・受け取り後に給与支給する事業所に配慮し、7月~6月での実施も認める
したがって一般的な実施期間は次の4通りとなるはずです。
処遇改善加算の配分 実際の実施期間
・4月~3月
・5月~4月
・6月~5月
・7月~6月
この部分も自治体により若干の判断差異があるため確認が必要です。一度この実施期間を決定すると「毎年度継続」する必要がある点に注意しましょう。
ポイント3.「加算のレベル」
ポイントの最後は加算のレベルです。介護職員処遇改善加算には1~3までのレベルがあり、給付の掛け率がそれぞれ定められています。
当社で支援している事業所では、原則として最高の加算レベルである加算1を推奨しています。文章で記載すると分かりにくいため、表で示します。
処遇改善加算1~3の要件
| 要件Ⅰ | 次の全てを行えますか? | 仕事内容と責任に応じた昇格制度を作る | ||
| 仕事内容と責任に応じた昇給制度を作る | ||||
| 上記を就業規則に定め全員に公開する | ||||
| 要件Ⅱ | 次のいずれかを行えますか? | 社内研修を実施し、能力確認を行う | ||
| 資格取得のための休暇や費用の一部補助 | ||||
| 要件Ⅲ | 次のいずれかを行えますか? | 定期昇給 | ||
| 保有資格で昇給 | ||||
| 能力評価で昇給 | ||||
| 加算1 | 加算2 | 加算3 | ||
| 要件Ⅰ | 〇 | ○ | いずれか | |
| 要件Ⅱ | 〇 | ○ | ||
| 要件Ⅲ | 〇 | - | - | |
この他に「職場環境等要件」への合致が求められますが、通常は問題なく対処できるため、ここでの解説は省略します。
・
処遇改善加算実績報告書作成上の注意点、ポイントは?
続いて介護職員処遇改善加算の「実績報告書」の作成上の注意点とポイントについて検討します。ここまでコラムを読み進めて頂いた方には、もうお分かりなるはずですが、処遇改善加算の実績報告では、「計画届で記載した内容がどのように実施されたか」を記載するだけです。
具体的には、「受取額<配分額」となったことを、詳細に記載します。実績報告書を正しく、かつ効率的に作成するためには、日ごろから次の2点を心がけましょう。
実績報告書を作成するためのポイント
1.毎月国から支給される処遇改善加算額を、指定種別ごとに分けて集計しておく
2.毎月対象職種に支給している処遇改善加算額を、指定種別ごとに分けて給与明細で記載する
ここで言う「指定種別ごとに」とは例えば1つの介護事業所で、訪問介護(介護保険)と居宅介護(障害福祉)を兼業しているような場合、指定種別ごとに「受取額<配分額」を達成する必要性があるためです。
処遇改善加算のサポートは社会保険労務士の専門分野
最後に、「介護職員処遇改善加算の手続きや管理の専門家は誰か?」という点についてご説明します。本コラムをご覧いただいてお分かりの通り、処遇改善加算の計画届、実績報告を適切に実施するためには、「労務関連の専門知識」と「介護・障害福祉分野に対する専門知識」が必要となります。
タスクマン合同法務事務所では、介護・障害福祉分野に専門特化している社会保険労務士、行政書士、税理士、司法書士が専門知識を総動員して、介護・障害福祉事業所をサポートしています。
介護職員処遇改善加算でお困りの際は、是非当事務所の無料相談を利用されることをお勧め致します。・
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】





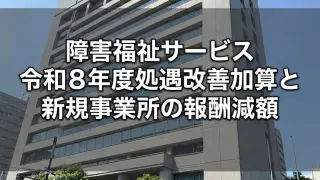


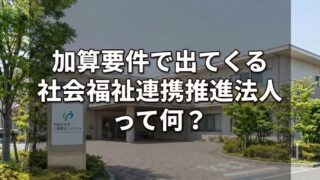


コラムサムネ02-320x180.jpg)


と人員配置加算(特定事業所加算・福祉職員配置等加算・サービス提供体制強化加算)の関係を分かりやすく解説-300x200.jpg)