特定処遇改善加算(2019年/令和元年10月スタート)の基礎知識|どのサイトよりも分かりやすく解説

-1.jpg)
-1.jpg)
特定処遇改善加算についての基礎知識を解説します。介護福祉職員の賃金改善を国費で補助する処遇改善加算。平成24年に交付金方式から現在の加算方式に変更された後、数度に渡り改正がありました。2019年(令和元年)10月から、処遇改善加算の上乗せとして、特定処遇改善加算が導入されました。
このコラムの推奨対象者
・2019年(令和元年10月)改正の特定処遇改善加算の概要を理解したい人
・特定処遇改善加算の適用要件を理解したい人
・特定処遇改善加算受給後の配分方法の仕組みを理解したい人
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化しています。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年7月現在、介護障害福祉事業の設立支援件数が、累積400社を突破。日々数多くのお客様から、処遇改善加算、特定処遇改善加算についてご質問を受け、ご対応しています。安心してお読み下さい。
- 1. 特定処遇改善加算とは?制度の趣旨を一言で説明
- 1.1. 制度の趣旨
- 1.2. 対象外の業種
- 2. 10年以上の介護福祉士がいなくてもOK?対象者を理解しよう
- 2.1. 勤続10年以上の介護福祉士問題について
- 2.2. つまり事業所の裁量で決めることができる!
- 2.3. 介護福祉士の資格保有は必須か?
- 2.4. 特定処遇改善加算(Ⅰ)にはサービス提供体制強化加算の最上位区分が必要
- 2.5. 特定事業所加算(Ⅰ)
- 2.6. 特定事業所加算(Ⅱ)
- 3. 特定処遇改善加算を職員に配分する方法。対象者を理解しよう
- 3.1. 配分の対象者
- 3.1.1. (Ⅰ)経験・技能のある介護職員への配分方法
- 3.1.2. (Ⅱ)他の介護職員
- 3.1.3. (Ⅲ)その他の職種
- 4. 中小企業には嬉しい特別措置も
- 5. 賃金改善(配分)以外の要件
- 5.1. 現行加算要件
- 5.2. 職場環境要件
- 5.3. 見える化要件(2020年4月から実施)
- 6. 特定処遇改善加算のまとめ
・
特定処遇改善加算とは?制度の趣旨を一言で説明
制度の趣旨
平成31年(2019年)4月12日付で厚生労働省から都道府県・市町村宛てに、「特定処遇改善加算の考え方」が通達されました。合計29枚の文書でなかなか分かりにくいですね。まずは制度の趣旨をご説明します。
特定処遇改善加算とは、一定キャリアの介護職員がいる場合に、現行の処遇改善加算に加えて加算が得られる制度です。現行の処遇改善加算同様、受給額以上を対象職種に配分する必要があります。(特定処遇改善加算の受給には、現行の処遇改善加算を算定している事が条件となります)
現行の処遇改善加算と大きく異なるのは、受け取る特定処遇改善加算を、その「一定キャリアの介護職員」だけでなく、その他の介護職員や事務職員にも配分できる点です。
訪問介護を例にとると、特定処遇改善加算率は(Ⅰ)で6.3%、(Ⅱ)で4.2%。対象事業所では有効な賃金施策です。具体的な計算方法は以下の通りです。
特定処遇改善加算の算定方法
基本サービス費に各種加算減算(現行の処遇改善加算を除く)を加えた額 × 加算率
対象外の業種
概ね全ての介護・障害福祉事業が適用対象となりますが、次の事業は対象外となります。(他にも対象外はある点に注意)
特定処遇改善加算の対象外事業
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅介護支援(ケアプランセンター)
・福祉用具貸与、販売
10年以上の介護福祉士がいなくてもOK?対象者を理解しよう
勤続10年以上の介護福祉士問題について
まずは人的要件から確認します。当初、報道でクローズアップされた要件は「10年以上の介護福祉士がいる場合」でしたが、これは必ずしも正確であるとは言えません。
厚労省通達のQ&Aには明確に「勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得可能である」と記載されています。それはどういう意味でしょうか?
「勤続10年以上の介護福祉士」とはあくまでも「基本的な考え方」であって、例えば次のようなキャリアでも問題ないわけです。
「勤続10年以上の介護福祉士」の考え方
・複数の法人にまたがる経歴でも通算10年ならOK
・介護事業所だけでなく医療機関の経歴も含まれる
・事業所内の能力評価や等級システムによっては10年未満でもOK
つまり事業所の裁量で決めることができる!
「勤続10年以上の介護福祉士」を制度上正式には「経験・技能のある介護職員」と呼びます。この「経験・技能のある介護職員」について、厚生労働省は下記の通り例示しています。
「経験・技能ある介護職員」についての厚労省通達
介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能などを踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。
キャリア10年というのは「およその目安」という趣旨ですね。
介護福祉士の資格保有は必須か?
厚生労働省の通達内のQ&Aには、「介護福祉士の資格を有する者がいない場合の措置」が記載されています。
Q&Aからは「介護福祉士不在でも特定処遇改善加算が取得可能」なように読み取ることができます。しかし制度の趣旨から考えると、これはあくまでも例外中の例外であると認識したほうが良いと思います。
特定処遇改善加算(Ⅰ)にはサービス提供体制強化加算の最上位区分が必要
特定処遇改善加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があります。それぞれの加算率を一覧表にすると、次の通りとなります。(令和2年7月時点)
| 主な指定種別 | 特定処遇(Ⅰ) | 特定処遇(Ⅱ) |
| 訪問介護 | 6.3 | 4.2 |
| 通所介護 | 1.2 | 1.0 |
| 居宅介護(障害) | 7.4 | 5.8 |
| 重度訪問介護(障害) | 4.5 | 3.6 |
| 生活介護 | 1.4 | 1.3 |
| 自立訓練(機能) | 5.0 | 4.5 |
| 自立訓練(生活) | 3.9 | 3.4 |
| 就労移行支援 | 2.0 | 1.7 |
| 就労継続A型 | 0.4 | 0.4 |
| 就労継続B型 | 2.0 | 1.7 |
| 共同生活援助 | 1.8 | 1.5 |
| 児童発達支援 | 2.5 | 2.2 |
| 放課後等デイサービス | 0.7 | 0.5 |
このうち、特定処遇改善加算(Ⅰ)の受給要件の一つに、「サービス提供体制強化加算の最上位区分を取っていること」が規定されています。(この要件を介護福祉士の配置等要件と呼びます)
この「サービス提供体制強化加算の最上位区分を取っていること」が、非常に複雑で分かりにくいので、別コラムで詳しく解説しています。
サービス提供体制強化加算とは、訪問介護事業を例にすると、「特定事業所加算の(Ⅰ)または(Ⅱ)」に当たります。さらに特定事業所加算の受給要件を簡単に説明すると以下のようになります。
特定事業所加算(Ⅰ)
下記のアで1つ、イで1つを同時に満たすこと
特定事業所加算(Ⅱ)
下記のア~イのうち、1つを満たすことと
特定事業所加算の要件
ア-1)介護福祉士の割合が30%以上
ア-2)介護福祉士+実務者研修等を修了している職員の割合が50%以上
イ-1)全てのサービス提供責任者が実務3年以上の介護福祉士
イ-2)全てのサービス提供責任者が実務5年以上の実務者研修修了等
この要件を満たすことが出来ない場合、特定処遇改善加算(Ⅰ)は受給できませが、特定処遇改善加算(Ⅱ)は受給可能性があります。詳細は本コラム後半で解説します。
特定処遇改善加算を職員に配分する方法。対象者を理解しよう
配分の対象者
次のステップでは、特定処遇改善加算の配分対象者を整理します。対象は大きく分けて3種です。
特定処遇改善加算の配分対象者
(Ⅰ)経験・技能のある介護職員(先に説明した勤続10年の介護福祉士のことです)
(Ⅱ)他の介護職員
(Ⅲ)その他の職種
これらの職員に対して、基本給、手当、賞与に分けて配分します。なお厚生労働省の通達では、基本給での配分が望ましいとされています。
(Ⅰ)経験・技能のある介護職員への配分方法
このカテゴリーの職員1人以上に、
・現行の処遇改善とは別に、特定処遇改善加算分として月8万円以上
・特定処遇改善加算分を支給後、年収が440万円以上
どちらかを実施しなければなりません。
ここで言う「8万円」には、事業主負担の法定福利費増加分は含めることができますが、「年収440万円」の方には法定福利費増加分を含めることができません。なお既に年収が440万円以上の職員がいる場合は、この条件は既に満たしていると判定されます。
また年収の算定について、法改正初年度(2019年度)は12カ月未満となるため、「12カ月特定処遇改善加算を受けていた場合の年収」で算定することが可能とされていました。
(Ⅱ)他の介護職員
特定処遇改善加算が従来の処遇改善加算と異なるは、配分方法の柔軟性にあります。
上記の(Ⅰ)経験・技能のある介護職員への「配分未満」であれば、他の介護職員に対しても特定処遇改善加算を配分することができます。
ここで比較する(Ⅰ)~(Ⅲ)の各職種への配分額については、平均値で比較します。平均値の算出には、配分を行わない者も分母に算入することに注意が必要です。
(Ⅲ)その他の職種
さらに介護職以外の一般事務職にも特定処遇改善加算を配分することができます。上記の(Ⅱ)他の介護職員の2分の1未満であることが要件です。ただし、
(Ⅱ)他の介護職員 > (Ⅲ)その他の職種の平均賃金
となっている場合には、本項の要件は既に満たしていると判定されます。また、「その他の職種の職員」に特定処遇改善加算を配分後、年収が440万円を上回る場合にも、算定対象とすることはできないことに留意しましょう。
中小企業には嬉しい特別措置も
中小企業で最もネックになるのが、
(Ⅰ)経験・技能のある介護職員1人以上に、
・現行の処遇改善とは別に、特定処遇改善加算分として月8万円以上
・特定処遇改善加算分を支給後、年収が440万円以上
どちらかを実施することだと思います。しかしこれには一定の配慮措置があります。つまり、
・小規模事業所で加算額全体が少額
・職員全体の賃金水準が低く、1人だけアップするのが困難
・規程の整備などに時間がかかる
このようなケースでは、例外的に「合理的な説明」を添付することで、上記要件を満たさなくても良い場合が認められています。該当する場合にはチャレンジしましょう。
賃金改善(配分)以外の要件
特定事業所加算の主な要件は先にご説明した通りですが、この他にも3つ要件があるので確認しておきましょう。
現行加算要件
現行の処遇改善加算のⅠ~Ⅲいずれかを取得していること。特定処遇改善加算と同時に取得することも可能なので、まだ取得していない場合は今すぐ準備を始めましょう。
職場環境要件
「資質の向上」、「労働環境処遇の改善」、「その他」の3カテゴリーからそれぞれ1つ以上の取組を行う必要があります。
現行処遇改善加算を得る際に既に実施している取組と重複してもOKです。詳細はここでは省略します。
見える化要件(2020年4月から実施)
特定処遇改善加算に基づく取り組みを、
・介護サービス情報公表制度(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)
・自社のホームページ
いずれかで公表していること。公表相手には当然ながら事業所職員も含まれます。
特定処遇改善加算のまとめ
特定処遇改善加算ではすべての要件を満たせば特定加算(Ⅰ)を、「介護福祉士の配置等要件」以外を満たせば特定加算(Ⅱ)を受給することができます。「介護福祉士の配置等要件」とは、先に説明した「特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を取っていること」を指します。
なお、当然のこととして労働基準法の遵守義務も併せて課せられているため、適切な労務管理が必要となることは言うまでもありません。
以上が特定処遇改善加算 の制度概要です。介護事業所にとって国費によって賃金改善ができる絶好の機会であると言えます。加算の取得には複雑な書類作成知識が必要となるため、手続きにお困りの方は是非当事務所までご相談を。
☑処遇改善加算に関連するコラム
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】





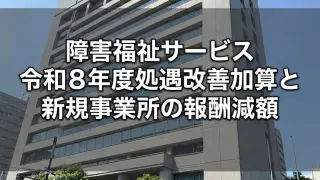


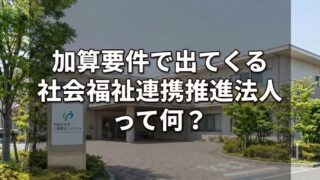


コラムサムネ02-320x180.jpg)

と人員配置加算(特定事業所加算・福祉職員配置等加算・サービス提供体制強化加算)の関係を分かりやすく解説-300x200.jpg)

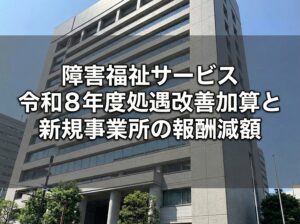
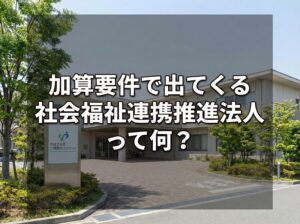

-300x224.jpg)



