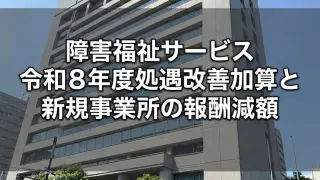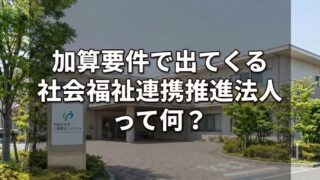【介護・障害福祉事業の営業先】開業後の営業活動はどこを回ればよいか?現役ケアマネージャーにその方法を聞きました。

-1.jpg)
-1.jpg)
介護・障害福祉事業の設立を支援する立場で、最も良く耳にするのが「どこに営業すればよいですか?」、「どんな営業ツールを使えば効果的ですか?」という質問です。このコラムでは、介護・障害福祉事業を開業したあと、どこに営業活動をすればよいかという問題について、現役ケアマネージャーへのインタビュー結果をもとに詳しく解説します。
☑このコラムの推奨対象者
〇訪問介護、訪問看護、デイサービスなどを新たに開業する方、開業直後の方
〇グループホーム、就労支援事業、生活介護などを新たに開業する方、開業直後の方
〇どこに、どのように営業活動、PR活動を行えばよいか、よくわからない方
☑このコラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は介護・障害福祉事業の開業支援に専門特化しています。このコラムをリライト(最終更新)した令和3年6月時点で、累積400社の介護・障害福祉事業の開業支援実績があります。このコラムは、現役介護支援専門員(ケアマネージャー)Yさんのご協力のもと「介護・福祉事業の営業先、営業手法」という内容について記載しています。執筆者のプロフィールは末尾にあります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談支援専門員が営業先
介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談支援専門員は、それぞれ要介護者、障害者のサービス利用計画の作成に深く携わる職種です。
〇介護保険サービスの利用者 → 介護支援専門員(ケアマネージャー)
〇障害福祉サービスの利用者 → 相談支援専門員
介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談支援専門員が作成するケアプランでは、特定のサービス提供事業者に偏ることなく、利用者の立場に立って公平な目線でサービス提供事業者をケアプランに組み込むことが求められます。ケアプランでは、
〇なぜその介護(障害福祉)サービスが必要だと判断したのか?
〇なぜその事業所を選んだのか?
以上の理由説明が義務付けられています。
ちなみに、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談支援専門員に、利用者紹介について金銭的便宜を図ることは法律で厳しく禁じられています。
同時に理解しておきたいのが、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談支援専門員側の「特定のサービス提供事業者への偏り」の問題です。ケアプランを作成する事業所から、特定のサービス提供事業者への案件比率について、様々な規制が存在することを理解しましょう。
実際に営業を受ける側の介護支援専門員(ケアマネージャー)にインタビューしました
ここでは、実際に様々な介護保険事業所から営業を受ける側の介護支援専門員(ケアマネージャー)のYさんに、インタビューした内容をお示しします。障害者に関する相談支援もほぼ同じ内容ですので、参考になると思います。
-
頻繁に営業活動をしてくる事業者さんには、やはり優先的に利用者の紹介をするものですか?
-
それはないですね。毎月数多くの介護保険事業者さんが営業活動にお見えですが、正直言って違いが分からないので「また営業に来られたな」という程度の認識にしかなりません。
-
ケアプランセンターの近くの事業者さんは、営業上有利になることはありますか?
-
それはあると思います。うち(ケアプランセンター)に近いということは、結果的に利用者さんの自宅にも近いわけですから。よほど専門的なサービス提供ができる、という以外は遠方の事業者さんには依頼しないと思います。近くの事業者さんの方が私たちケアマネにとっては、何かと便利ですから。
-
アポなしの飛び込み営業についてはどう思いますか?
-
正直って迷惑以外のなにものでもありませんね(笑)。営業する側としては、電話アポで断られるのを避ける点や、効率的にローラー作戦で営業廻りをする点を重視して、アポなし飛び込み営業をされるんでしょうが、我々ケアマネージャーも忙しいので、飛び込み営業はハッキリ言って迷惑です。
-
ということは、やはり電話で事前にアポを入れたほうが良いのですか?
-
それが良いと思います。例えば「○○町〇丁目に今度オープンした訪問介護事業所です。」という名乗りでご挨拶頂ければ、我々としても近所で長いお付き合いになるので、邪険にアポイントをお断りする、ということもありません。
-
いわゆる営業ツールについてお尋ねします。名刺やチラシ、ホームページなど、どんな工夫をお勧めしますか?
-
ご面談後にすぐホームページを見に行く、ということはしませんので、やはり名刺が重要だと思います。事業所の顔ですから。名刺はなるべく専門業者さんに作ってもらうことをお勧めします。「手作りの名刺」と分かるような出来だと、安心して利用者さんをお任せしにくいので。会社名がなく、事業所名だけの名刺がたまにありますが、会社名も記載する方が良いと思います。
-
メールアドレスについてはいかがですか?
-
よくある、GmailやYahooメールなどの、無料で使えるメールアドレスも信頼感に欠けますね。できればきちんと自社のドメイン※でメールアドレスを取得されると良いと思います。
※ドメインとは、@以下の部分を指します。
-
チラシに関してはいかがですか?
-
名刺に書ききれないような、例えば事業所のPRポイントや、代表の方の経歴、創業に至った経緯などがあれば、A4三つ折りくらいのチラシはあった方が効果的だと思います。ただお金がかかるので、無理して作らなくても良いと思います。
-
ホームページに関してはいかがですか?
-
ホームページは「事業所名 + 地域」で検索することになると思います。例えば「介護センター○○ 大阪市○○区」みたいに。ホームページを作ったら、自分で一度検索してみて、そのキーワードでちゃんと一番に出てくるかどうか、チェックされると良いと思います。ここで一番に出てきたら、信頼感が湧きますね。
-
会社のロゴマークなどがあると、信頼感は高まりますか?
-
20社に1社くらい、きちんとした会社ロゴマークを名刺やチラシに入れていらっしゃるところがありますね。そういう事業者さんは真剣度合いが伝わってきますね。
-
一度利用者さんの紹介などでお使いが始まった後の工夫について教えてください
-
やはり情報の報連相をきちんとする、会議には遅れず参加する、等の積み重ねで、事業者さんの評価が分かれます。実際に、報連相や会議参加がルーズな事業者さんは、利用者に対するサービス提供もルーズでしょうから、継続してお付き合いすることはまずありません。逆にしっかりとした情報連携をして下さる事業者さんとは、末永くお使いさせてもらっています。
-
最後に、これから介護・障害福祉事業を立ち上げる方にメッセージがあればお願いします
-
高齢者、障害者ともにサービス利用の需要はこれからも増すでしょうが、それに伴ってサービス提供事業者さんの数も増えています。競争を勝ち抜くためには、表面的な営業活動ではなくて、実際のサービス提供の中で信用を積み重ねるしかないと思います。際しい道のりですが、頑張ってもらいたいと思います。
インタビューにご協力頂きました介護支援専門員(ケアマネージャー)のYさん、ご多忙の折にありがとうございました。
営業活動をする前に持つべきマーケティング志向とは?
さて、ここでは少し視点を変え、マーケティング目線で介護・障害福祉事業の営業を考えてみます。Yさんから頂いたアドバイスを前提にします。
介護・障害福祉事業の分野では、働く人たちの労働条件の改善が一向に進まず、離職し自ら創業する人が後を絶ちません。まさに小規模乱立時代を迎えています。介護支援専門員(ケアマネージャー)のYさんが言うように、サービス利用者の数も増加傾向にあるとはいえ、争奪戦には変わりありません。
ここであなたに持ってもらいたいのが、マーケティング志向です。
あなたの事業は後発組、小規模、地域密着型です。だからこそ、差別化戦略を主軸としたマーケティング志向を持たねばなりません。マーケティング志向を持たずに創業することは、大手事業者や既存事業者に対して、武器を持たずに丸腰で戦いを挑むのと同じことです。
あなたの介護・障害福祉事業の定義を考えましょう
マーケティングを考える上で参考となるのが、4つのPに基づくフレームワークです。マーケティングで言う4つのPとは、
〇製品(Product)
〇価格(Price)
〇流通(Place)
〇販促(Promotion)
を指します。つまり、何を(Product)、いくらで(Price)、どのような手法・場所で(Place)売るか。そしてその販促方法(Promotion)をどう考えるか、というものです。
介護・障害福祉事業では、「いくらで(Price)」は国が単位という考え方で固定化しており、またサービス業であるため、そもそも「流通(Place)」という考え方が発生しません。実質的には2つのP(製品・販促)のみとなります。この2つを軸に、
〇あなたの事業の強み
〇あなたが創業するきっかけ
を問い直しましょう。
ある化粧品会社が「当社が売っているのは化粧品ではなく、希望である」と表現したことがあります。つまり、この会社は単に化粧品を製造、販売しているのではなく「全ての女性に対する希望という価値を提供しているのだ」という意味です。
この化粧品会社のように、あなたも自社の事業の定義を考えなくてはなりません。あなたの事業が売るのは、表面的には例えば「訪問介護サービス」かもしれませんが、その真実は
〇利用者の尊厳
〇終末期の人生の平穏
〇ご家族の人生設計のお手伝い
かもしれないわけです。
どのようなサービスを、どうやって売っていくか?
それでは具体的にマーケティング4つのPについて考えてみます。先ほどご説明の通り、介護・障害福祉事業では価格(Price)、流通(Place)の2つのPが除外され、実質的には残り2つのP、つまり製品(Product)、販促(Promotion)となります。
そこで、
(製品)どのようなサービスを売るのか
(販促)どうやって利用者を獲得するのか
の2つに絞って考える必要があるわけです。小規模、地域密着型事業でのキーワードは他社が真似できない差別化戦略となります。
当社(タスクマン合同法務事務所)では、
行政書士・社会保険労務士・税理士・司法書士の合同事務所による、介護・障害福祉事業専門の設立サポート
で差別化しています。この条件を満たすことのできる同業他社は、おそらく日本中を探してもごく少数だと思います。つまり当社は圧倒的な差別化が実現できているわけです。
あなたの場合も、一番得意な分野に焦点を絞って、事業の定義づけを行いましょう。例えばこんな感じです。
〇認知症ケア経験10年のサ責がサービスを統括します!
〇緩和ケア経験豊富な看護師が多数在籍!
〇重度障害者のケアはお任せください!
それらを思い切って、会社のPRパンフレットや名刺に書きましょう。このようにして製品(Product)を決めていきます。
良い噂(口コミ)の拡大を目指しましょう
次に販促(営業)です。介護支援専門員(ケアマネージャー)のYさんが言うように、最初の出会いは名刺やチラシ、ホームページであったとしても、長期的な関係性を築くためには、良いサービス提供を心掛け、介護支援専門員や相談支援専門員の信頼を獲得する以外にありません。
先に述べましたが、あなたの事業は小規模、地域密着のはずです。その場合に欠かせない差別化戦略は、何といっても「口コミ」です。良いサービス提供を心掛けるのと同時に、ちょっとした努力で良い口コミが広がるような戦略的工夫をしましょう。例えば、
〇サービス提供後、庭先で1分間掃き掃除をして帰る
〇月に1度、管理者が巡回し、利用者からアンケートを取る
〇ケアマネージャーに、直筆で定期的な挨拶状を送る
などです。小さな努力の積み重ねで、良い口コミが広まるように戦略的に工夫しましょう。
ちなみに、悪い口コミは、良い噂の10倍のスピードで広まっていきます😓
このコラムのまとめ
このコラムでは「介護・障害福祉事業の営業先はどこを回ればよいか?」との問いに端を発して、マーケティング戦略・差別化戦略についてご説明してきました。
これらの考え方のフレームを軸に、ぜひ思考の整理をして頂きたいと思います。
あなたの事業が成功裏にスタートを切ることを切に願っています。
5万円で会社設立&指定申請
介護障害福祉事業 会社設立オールインワンパッケージは、会社設立、指定申請ほか、開業に必要となる全ての法手続きをパッケージにしたサービスです。詳細は左の画像をクリックしてご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】