介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座⑤|遺産分割の方法に関する法律上の定めについて
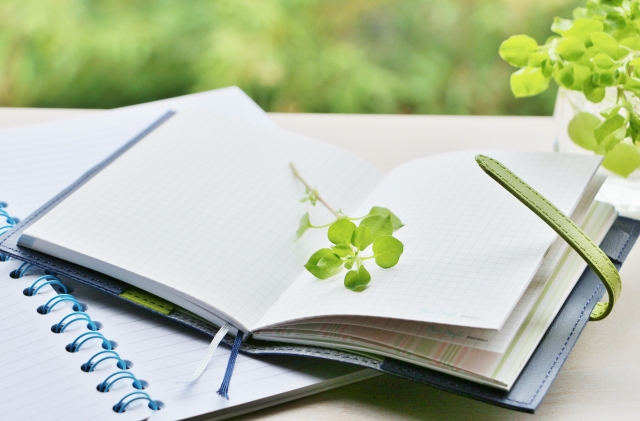
■遺産分割の方法は法律で示されているのか?
1.遺産分割方法を示す民法906条
民法906条
「遺産分割をする際には、次の項目を考慮しましょう。」
①遺産の種類、性質
②各相続人の年齢・職業
③各相続人の心身の状態
④各相続人の生活状況
⑤その他一切
こういうものを考慮して分割すべきということが、実は民法に示されていたわけです。
2.協議分割においては単なる指針に過ぎない
とはいえ、906条は協議分割においては「単なる指針」に過ぎません。
「相続人の話し合いで解決する」という「協議分割」、「調停分割」の場面ではあくまでも相続人の自由意思が尊重されますので、基本的には「誰が」、「何を」相続するかは自由です。
しかし「審判分割」になると話は別です。
審判分割では家庭裁判所が分割を主導しますので、基本的には906条に沿った分割がなされます。
審判分割で906条違反の判断が下された場合には上級裁判所で争うこともできます。
■事例で読む民法906条の遺産分割方法
1.ケーススタディ~遺産分割の方法


Aの相続人はW(妻)、BCD(ともに子)である。
相続人の状況は次の通り。
Wは高齢の専業主婦であり、外部で働くための職業能力がない
BはAの事業を長年手伝っている
Cは不動産会社を経営している
Dは企業勤めで借家に住んでいる
遺産の状況は次の通り
AとWが住んでいた家屋
Aの経営する会社の株式
賃貸用マンション
多額の現金
2.解説~遺産分割の方法
もしあなたが家庭裁判所の裁判官だとしたら、906条をもとにどのように相続させますか?
906条は「審判分割」でこそ有効性を持つとはいえ、合理的な考え方に基づく指針です。
この考え方を無視した遺産分割協議は、きっと後日に禍根を残すはずです。
遺産分割協議が始まったら、まず906条を全員で確認しあうことをお勧めします。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538

コラムサムネ02-320x180.jpg)
-コピー-320x180.jpg)
|人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練コラムサムネ-320x180.jpg)
-320x180.jpg)


