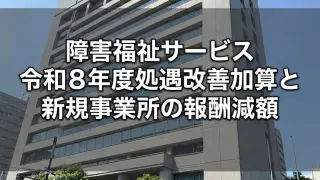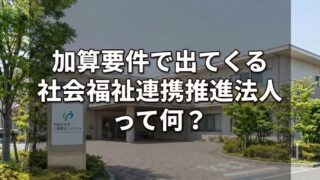介護保険の【支給限度基準額】とは?介護保険給付と支給限度基準額を徹底解説!介護事業起業者のための開業講座③

-1.jpg)
-1.jpg)
近い将来、介護保険事業の立ち上げを考えておられる方に向けて「介護事業起業者のための開業講座」と題して、連載企画をお届けします。第3回のテーマは「介護保険給付と支給限度基準額」です。特に区分支給限度基準額について詳しく解説します。
このコラムの推奨対象者
・介護サービスの「現物給付と償還払い」の違いを整理したい人
・介護給付と予防給付の「種類」を理解したい人
・「区分支給限度基準額」について知りたい人
・「福祉用具購入費、住宅改修費および種類支給限度基準額」について知りたい人
・「支給限度基準額が設定されないサービス」について知りたい人
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数67名、累積顧客数は北海道から沖縄まで746社、本社を含め8つの営業拠点で運営しています。コラムでは介護保険給付と支給限度基準額について詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
全7回の開業講座シリーズはこちら
介護サービスの現物給付と償還払い
初めに介護保険の給付方法について解説します。介護保険の給付方法は「現物給付」と「償還払い」に分類することができます。
訪問介護を例に「現物給付」をご説明します。利用者負担割合1割の人が10,000円分の訪問介護サービスを利用した場合、自己負担額1,000円を訪問介護事業者に支払い、市町村等の保険者が訪問介護事業者に9,000円を支払う。これが「現物給付」です。


一方「償還払い」では、利用者がいったん全額を事業者に支払い、後日市町村等の保険者から利用者に9,000円償還されます。償還払いは福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費などに限定されており、その他は全て「現物給付」となります。


介護給付と予防給付
前の項目では、介護保険の給付方法を解説しましたが、次に保険給付の種類について解説します。介護保険の給付は、要介護1~5の認定を受けた人に対する「介護給付」と、要支援1または2の認定を受けた人に対する「予防給付」に大分類されます。


さらに介護給付は4つに分類されます。具体的には訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与などの居宅サービス、介護老人福祉施設(別名特養)、介護老人保健施設(別名老健)などの施設サービス、市町村が実施する地域密着型サービス、要介護者のケアプランを担う居宅介護支援です。
一方の予防給付は、施設サービスを除く3つの介護給付に紐づきます。つまり、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援です。
この内、訪問介護と通所介護については、平成29年に介護保険の予防給付から除外され、市町村が独自に行う総合事業に移行しました。総合事業については別で解説します。
区分支給限度基準額
続いて、介護給付と予防給付の利用限度額について解説します。以下の説明では、介護給付と予防給付をまとめて保険給付と呼ぶことにします。
保険給付は限度なく利用することはできず、一部のサービスを除き利用限度額が定められています。その利用限度額のことを支給限度基準額と呼びます。「支給限度基準額が設定されない一部のサービス」については本編の最後に解説します。


支給限度基準額は4つのカテゴリーで定められていますが、そのうち最も重要となる「区分支給限度基準額」を中心に解説します。
区分支給限度基準額は要介護1から5、および要支援1、2の合計7つの区分ごとに、1カ月あたりの利用限度額が定められています。令和6年度の例で言うと、最も高い要介護5で36,217単位、最も低い要支援1で5,032単位となります。1単位概ね10円として、最大要介護5で約36万円、最低要支援1で約5万円です。


月の途中で初めて要介護又は要支援認定を受ける場合、日割り計算は行わず、たとえその月の日数が少ない場合でも、1カ月分の区分支給限度基準額まで利用することができます。


また月の途中で要介護度または要支援度が変更された場合、その月は重い方の区分支給限度基準額まで利用できるという配慮がなされています。


区分支給限度基準額は国が全国一律に定めますが、各市町村がその上乗せ部分を条例で定めることが認められています。地域の実情に応じた対策を講じることができるわけです。


ここで国の政策上の配慮により、区分限度支給額の対象から除外されている加算制度をご紹介しておきます。
交通の便が悪い地域に対応するための特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、医療ニーズに対応するための緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、介護職員の処遇改善に対応するための処遇改善加算、サービス提供体制強化加算などは、それぞれの加算目的に配慮し、区分支給限度基準額の対象から除外され、別枠で計算されます。


訪問介護における特定事業所加算も「区分支給限度基準額の対象から除外すべき」との声が挙がっていますが、令和6年時点では除外されていません。そのため、特定事業所加算を算定できるにもかかわらず、算定していない事業所が多数存在することが問題視されています。
特定事業所加算算定により、サービス利用が区分支給限度基準額を超えてしまい、利用者負担が増大することを避けたい、との思惑が働いていることが厚生労働省の調査により明らかになっています。今後の制度改正を期待したいところです。
福祉用具購入費、住宅改修費および種類支給限度基準額
ここでは区分支給限度基準額以外の3つの支給限度基準額を簡単に解説します。


福祉用具を購入する場合、4月から翌年3月末までの1事業年度で、10万円が利用上限となります。この上限のことを「福祉用具購入費支給限度基準額」と呼びます。福祉用具購入費支給限度基準額も、各市町村がその上乗せ部分を条例で定めることが認められています。
住宅改修について保険給付を受ける場合、1つの住宅について20万円が利用上限となります。この上限のことを「住宅改修費支給限度基準額」と呼びます。住宅改修費支給限度基準額も、各市町村がその上乗せ部分を条例で定めることが認められています。
ある特定の介護サービスが不足している場合に、希望する利用者が公平に介護サービスを利用できるよう、市町村が上限を定める場合があります。この上限のことを「種類支給限度基準額」と呼びます。種類支給限度基準額については、設定時点で市町村が地域の実情に応じて限度額を予め決定するため、上乗せ支給の概念自体が生じない点も理解しておきましょう。
以上、支給限度基準額について解説しましたが、訪問介護、訪問看護、通所介護等の居宅サービスでは、区分支給限度基準額を中心に理解しておけば良いでしょう。
支給限度基準額が設定されないサービス
本編の最後に「支給限度基準額が設定されないサービス」について解説します。


施設入所系サービス
介護老人福祉施設(別名特養)、介護老人保健施設(別名老健)などの施設入所系サービスでは、要介護度別に1日あたりの単位数が定められており、他の保険給付を組み合わせる必要がありません。そのため施設入所系サービス(短期利用を除く)では、支給限度基準額を定める必要がないわけです。
居宅療養管理指導・居宅介護支援
居宅療養管理指導は、通院が困難な在宅療養者に対して医師、看護師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。居宅介護支援とはケアプランのことです。ここでは要支援者に対する介護予防支援も含みます。
居宅療養管理指導およびケアプランでは、予め1カ月当たりの単位数が設定されているため、支給限度基準額を定める必要がありません。
結論として、施設入所系サービス(短期利用を除く)、居宅療養管理指導、ケアプラン以外の保険給付には、支給限度基準額が定められていると理解しましょう。
まとめ
介護事業起業者のための開業講座、第3回では「介護保険給付と支給限度基準額」について解説しました。最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。
会社設立・運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】