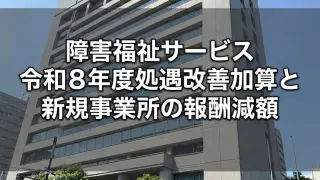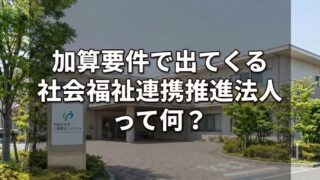要介護認定3つの申請【新規・区分変更・更新】の違いと実際の認定申請の流れを解説!介護事業起業者のための開業講座②

-1.jpg)
-1.jpg)
近い将来、介護保険事業の立ち上げを考えておられる方に向けて「介護事業起業者のための開業講座」と題して、連載企画をお届けします。第2回のテーマは「要介護認定3つの申請(新規・区分変更・更新)の違いと実際の認定申請の流れ」です。介護保険サービスを利用する前段階の、要介護認定の仕組みについて詳しく解説します。
このコラムの推奨対象者
・要介護認定3つの申請(新規・区分変更・更新)の違いを整理したい人
・要介護認定の「申請」ができる人の定義を理解したい人
・要介護認定申請の「審査」を行う人(組織)について知りたい人
・要介護認定等の不服申立先(審査機関)について知りたい人
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数65名、累積顧客数は北海道から沖縄まで746社、本社を含め8つの営業拠点で運営しています。コラムでは要介護認定3つの申請(新規・区分変更・更新)の違いと実際の認定申請の流れについて詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
全7回の開業講座シリーズはこちら
要介護認定3つの申請(新規・区分変更・更新)の違いは?
初めに、要介護認定の3つの申請種類について確認しましょう。要介護認定には次の3つの申請区分があります。
要介護認定の3つの申請種類
①初めて申請する場合:「新規」
②認定期間中に現在の認定区分を変更する場合:「区分変更」
③有効期間後の継続を希望する場合:「更新」
以下、有効期間の違いを解説しますが、新規認定と区分変更認定は、制度上同じ取り扱いになるため、ここからは新規認定と更新認定に絞って解説します。原則的な有効期間としては、新規の場合6カ月、更新の場合12カ月となります。


ただし、申請時点で、短期的な要介護状態の変化が見込まれる場合があります。具体的には病状が急速に悪化している最中で、2~3カ月後には要介護状態が変わっている可能性が高い場合等です。
このような場合には、有効期間を短縮することが認められています。具体的には新規の6カ月、更新の12か月をそれぞれ、最短3カ月まで短縮することが可能です。このように要介護認定期間を予め短縮しておくことで、次回の確認を早めに行うことができるわけです。


一方、申請時点で、要介護状態が長期的に固定化しており、今後も大きな変化がないと見込まれる場合、有効期間を延長することが認められています。具体的には新規の6カ月を最長12カ月に、更新の12か月を最長24カ月まで延長することが可能です。さらに、更新の場合でかつ要介護度が変わらないと見込まれる場合には、最長36カ月まで延長することが可能です。このように要介護認定期間を予め延長しておくことで、認定更新の頻度を減らし、手続きを簡略化することができるわけです。


なお、要介護認定期間の「効力開始日」については、新規と更新で違いがあるので注意しましょう。具体的には、新規の場合は「申請日」が、更新の場合は「有効期間満了日の翌日」が効力開始日となります。つまり新規の場合、申請日から認定日まで約1カ月の審査期間が空くことになりますが、認定されれば申請日に遡って、要介護認定の効力が生じるという意味です。


要介護認定の「申請」ができる人は誰か?
続いて、実際の要介護認定の申請について解説します。申請手続きは1号被保険者と2号被保険者で違いがあります。第1回で解説した通り、1号被保険者とは市町村または東京23区内に住民票がある65歳以上の人、2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の人のうち、医療保険の加入者です。
1号被保険者の要介護認定申請には、特別の制限はありません。要介護認定申請を行いたい意思があれば、誰でも申請することができます。一方、2号被保険者が要介護認定申請を行うためには、介護保険法施行令で定める16の特定疾病のいずれかを発症していることが要件となります。具体的にはがん、関節リウマチ、ALS等です。


つまり、2号被保険者については、これらの特定疾病を発症している場合に限り、要介護認定申請を行うことができるわけです。なお、申請は本人のほか、家族、介護保険施設、当社のような社会保険労務士等が代行することも可能です。
要介護認定申請の「審査」を行う人(組織)は誰か?
続いて、要介護認定申請の審査について解説します。要介護認定申請が提出された場合、一次判定、二次判定を経て、要介護認定が行われます。
一次判定は全国一律の認定調査票に基づき、認定調査員が「基本調査」と「特記事項」に分けて認定調査を行います。認定調査員は新規認定の場合、市町村の職員ですが、更新認定の場合は居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、外部委託することが認められています。
一次判定のうち、基本調査部分は74項目あり、それらをシステム入力することで自動的に判定されますが、基本調査部分だけでは本人の状態を正しく判定することができないため、「特記事項」で補足する形となります。


二次判定は保険者、つまり市町村および東京23区に設置される「介護認定審査会」が実施します。具体的な審査としては、一次判定の結果、つまり基本調査と特記事項に加えて、主治医の意見書により判定を行います。


主治医の意見書については、保険者から本人の主治医に意見を求めることになりますが、主治医がいない場合は保険者が指定する医師等の診断を受け、その結果を参考にする形となります。
一次判定、二次判定を経て、保険者が要介護認定を行いますが、申請から認定まで、原則30日以内に完了することが定められています。
なお、申請者本人に要介護認定の「区分変更」の申請が認められる一方、保険者側にも職権による「認定区分の変更」、または要介護認定自体の「取消」を行うことが認められている点も理解しておきましょう。
要介護認定等の不服申立先(審査機関)は?
本編の最後に、要介護認定等の不服申立先について解説します。介護保険の利用者が、保険者つまり市町村または東京23区の判断に対して不服がある場合、その不服申立を審査するために、都道府県に「介護保険審査会」が設けられています。
_介護認定3つの申請【新規・区分変更・更新】の違いと実際の認定申請の流れを解説!介護事業起業者のための開業講座②.png)
_介護認定3つの申請【新規・区分変更・更新】の違いと実際の認定申請の流れを解説!介護事業起業者のための開業講座②.png)
介護保険審査会の審査内容としては、被保険者証の交付、要介護認定、介護保険料の徴収などが対象となります。
前の項目で解説した「介護認定審査会」と名称が似ているため、その違いを正しく理解しましょう。介護認定審査会は保険者に設置される「要介護認定申請」の審査機関、介護保険審査会は都道府県に設置される「不服申立」の審査機関です。
補足的に、名称が類似している審査機関として、「介護給付費等審査委員会」についてもご紹介しておきます。
「介護給付費等審査委員会」は国民健康保険団体連合会、通称「国保連」に設置される審査機関です。介護給付費等審査委員会では、介護事業者が発行する、介護給付費請求書等についての審査を行います。


以上、ご紹介した3つの審査機関の名称とその審査内容の違いについて、誤解のないように知識を整理しておきましょう。
まとめ
介護事業起業者のための開業講座、第2回では「要介護認定3つの申請(新規・更新・区分変更)の違いと実際の認定申請の流れ」について、特に介護保険サービスを利用する前段階の、要介護認定の仕組みを解説しました。
会社設立・運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】