介護保険の被保険者と住所地特例とは?他の制度利用による被保険者適用除外と給付調整とは?介護事業起業者のための開業講座①

-1.jpg)
-1.jpg)
近い将来、介護保険事業の立ち上げを考えておられる方に向けて「介護事業起業者のための開業講座」と題して、連載企画をお届けします。第1回のテーマは「介護保険の被保険者と住所地特例、他の制度利用による被保険者適用除外と給付調整」です。主に介護保険サービスの対象となる方の範囲について詳しく解説します。
このコラムの推奨対象者
・介護保険の被保険者の定義を理解したい人
・被保険者から適用除外される方の定義を理解したい人
・住所地特例の制度を詳しく整理しておきたい人
・給付調整の優先度について不安のある人
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数63名、累積顧客数は北海道から沖縄まで744社、本社を含め8つの営業拠点で運営しています。コラムでは介護保険の被保険者と住所地特例、他の制度利用による被保険者適用除外と給付調整について詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
全7回の開業講座シリーズはこちら
介護保険の被保険者
初めに介護保険の被保険者から確認しましょう。「被保険者」とは、つまり介護保険制度の加入者のことです。これに対して「保険者」という考え方があります。介護保険制度の「保険者」は市町村と東京23区です。保険者については、別で取り上げますので、ここでは被保険者について解説します。
介護保険の被保険者は、大きく分けると2つに分かれます。1号被保険者と、2号被保険者です。


1号被保険者とは、市町村または東京23区内に住民票がある、65歳以上の人です。2号被保険者とは、市町村または東京23区内に住民票がある、40歳以上65歳未満の人のうち、医療保険の加入者です。医療保険とは、会社勤めの方は会社の健康保険、会社勤めでない方は国民健康保険が該当します。
わが国では「国民皆保険」という大原則があります。つまり、生まれたての赤ちゃんから、高齢者に至るまで、全国民が何らかの医療保険に加入するというのが、「国民皆保険」の考え方です。「国民皆保険」が大原則なのに、なぜあえて介護保険の2号被保険者で、医療保険加入者を要件としているのか、この点について考えてみます。
繰り返しになりますが、2号被保険者の要件は、「市町村または東京23区内に住民票がある、40歳以上65歳未満の人のうち、医療保険の加入者」です。40歳以上、65歳未満の人のうち、会社勤めの方は会社の健康保険、その扶養親族も、会社の健康保険に加入します。
一方で会社勤めでない方は国民健康保険に加入するわけですが、国民健康保険にはいくつかの「適用除外者」が定められており、その中に「生活保護世帯」が含まれています。つまり、40歳以上65歳未満の生活保護世帯は、国民健康保険に加入できず、それに連動して、介護保険制度の2号被保険者にもなれないわけです。
このように、生活保護世帯は介護保険制度での介護サービスを受けることができませんが、生活保護法の方で、介護保険サービスと同等の「介護扶助」を受けることができます。この点は別で詳しく解説します。
以上が介護保険の被保険者の定義です。ここまでの解説でお分かりの通り、「国籍」はそもそも要件とされていません。つまり外国籍であっても、市町村または東京23区内に住民票がある方は介護保険の被保険者となる場合があり、逆に日本国籍であっても海外在住のため、日本に住民票がない場合は被保険者とならない場合があります。
「単に国籍だけでは、介護保険の被保険者判定はできない」という点を理解しておきましょう。
被保険者からの適用除外
介護保険制度は公的保険であるため、本人の自由意思で加入または非加入の選択を行うことはできません。介護保険法の被保険者は、先ほど解説した通り、1号被保険者、2号被保険者のみです。


一方、介護保険施行法、施行規則では「1号被保険者または2号被保険者に該当しつつも、当分の間、介護保険の被保険者から除外される人」が定められています。それが「適用除外施設入所者」です。適用除外施設とは例えば、障害者支援施設、ハンセン病療養所、生活保護救護施設などが該当します。
これら「適用除外施設入所者」については、介護保険の1号被保険者、または2号被保険者の要件に該当する場合であっても、それぞれの施設に長期入所し、介護保険と同等のサービスが提供されていることから、例外的に介護保険の被保険者から除外されているわけです。
住所地特例
ここでは介護保険制度の「住所地特例」について解説します。介護保険の1号被保険者、2号被保険者ともに、基本要件が「市町村または東京23区内に住民票があること」である点は、先ほどご説明した通りです。


このことにより、その人の住民票が置かれている市町村または東京23区が保険者となり、保険給付をはじめ、様々な事務を取り扱います。ある要介護者が住民票を自宅のあるA市に置きつつ、B市の介護保険施設に入居した場合でも、保険者はA市のままです。住民票所在地で判定するためです。
それでは、要介護者が住民票を介護保険施設に移した場合、保険者はどうなるでしょうか。仮に保険者がB市に変わると、保険者としてのB市の負担が増大します。多数の介護保険施設が存在する市の負担増大にも繋がり、財政上の不均衡を招きます。
この問題を是正するのが、「住所地特例」の考え方です。住所地特例が適用される場合、介護保険制度の大原則である、「住民票所在地=保険者」に例外が生じます。具体的に解説します。
住所地特例の適用のためには、被保険者が「住所地特例対象施設」に入居し、そこに住民票を移すことが前提となります。住所地特例対象施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホームなどです。サ高住については有料老人ホーム型の場合のみ、対象施設となります。


このような場合、保険者は「住所地特例対象施設」へ住民票を移す前、つまり自宅があった市町村または東京23区のままです。具体例で言うと、住民票が、A市の自宅からB市の対象施設、C市の対象施設へと移った場合でも、保険者は対象施設入居前のA市のままです。
このように住所地特例制度を設けることで、対象施設が多数存在する市町村または東京23区の、保険者としての負担集中を避けることに繋がっているわけです。
給付調整
本編の最後に「給付調整」について解説します。「給付調整」とは、介護保険サービスと、その他の公的制度によるサービスが重複する場合に、調整を図るための仕組みです。


具体例として、介護保険サービスと障害福祉サービスの重複を取り上げてみます。要介護認定を受けつつ、同時に身体障害者手帳を持つ人が、居宅での介護を必要とする場合、それぞれの制度から二重の介護サービスを受けることはできず、また本人の希望でどちらか一方を選択することもできません。この場合、介護保険サービスが障害福祉サービスに優先します。
ここでは介護保険サービスを含む、合計10の類似サービスについて、適用の優先関係を整理しておきます。


例えば介護保険サービスが、生活保護法、障害者総合支援法などで提供可能なサービスと重複する場合、介護保険サービスが優先します。ただし介護保険制度には、障害者総合支援法で行う移動支援、同行援護、行動援護などが存在しません。このように介護保険法にないサービスについては、給付調整の考え方自体が発生せず、障害者総合支援法のサービスを利用することになります。
一方で、介護保険法に対して優先的に適用される制度としては、労災給付や国家補償給付などが存在します。
以上の優先関係を確認した上で、利用者がどのサービスを受けることができるのか、情報を正しく整理しましょう。
まとめ
介護事業起業者のための開業講座、第1回では「介護保険の被保険者と住所地特例、他の制度利用による被保険者適用除外と給付調整」について、特に介護保険サービスの対象となる方の範囲を解説しました。
会社設立・運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】








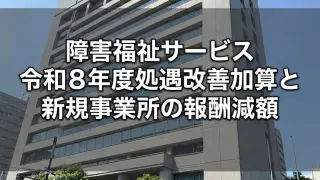


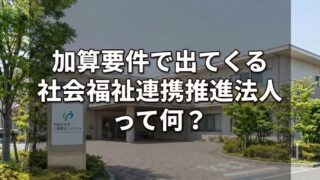










様-300x233.jpeg)