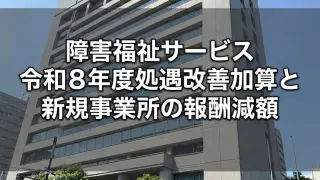介護障害福祉事業を開業する方向けの遺言講座⑦|遺留分侵害 遺留分権利者と遺留分対象財産

■遺留分は私法の大原則に対する制限
1.私法(民法)の大原則とは?
公法。つまり公の制度を規定する代表格が憲法です。
これに対して私法の代表格は民法です。
私法とはつまり、私人間の取引を規定する法律です。
近代私法の3原則と呼ばれるものに、
①権利能力平等(人は平等に権利行使できる)
②私的自治(私人間の取引は原則自由)
③所有権絶対(所有権は絶対的な権利)
という考え方があります。
遺留分はそのうち、②私的自治、③所有権絶対の原則に対する例外と言えます。
しかし、②③に対する制限が効力を発するのが、
「本人(被相続人の)の死後」という点が特徴的です。
2.遺留分とは何か?
本人(被相続人)は遺言で誰に何を相続させるか自由に指定することができます。
また、生前贈与も本人(被相続人)の自由です。
しかし、この「自由」を無制限に認めてしまうと、被相続人と生活を共にした遺族の生活が脅かされてしまう可能性があります。
「家族相互扶助」
という民法の考え方に反するわけです。
そこで、一定の法定相続人に、最低限の相続権を認めました。
遺言等によっても、侵すことのできない権利です。
それが遺留分です。
■遺留分権利者
1.だれが遺留分権利者か?
遺留分権利者は「兄弟姉妹以外の相続人」です。
つまり、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)です。
遺留分は相続人に限られるため、先順位の相続人がある場合に、後順位の相続人に遺留分はありません。
2.ケーススタディ~遺留分権利者


Aには兄、父母、妻、子の5名の肉親がある。
Aは「死後、全財産を○○市に寄付する」と遺言して死亡した。
3.解説~遺留分権利者
この場合、遺留分権利者は、
妻・子のみです。
兄、父母がいかにAの遺言に納得がいかなくても、遺留分の権利がないため、○○市に対する遺留分減殺請求はできません。
4.相続欠格、廃除、相続放棄者の遺留分
相続欠格、廃除は被相続人との信頼関係を損なった者に対する制裁ですので、遺留分を認める余地はありません。
相続放棄も、「初めから相続人でなかった事にする」制度ですので、遺留分はありません。
5.胎児の遺留分
胎児は「生誕する(死産ではない)」ことを条件に相続人となるため、遺留分に関しても、「生誕する」場合に限り認められます。
6.代襲相続人の遺留分
相続欠格、廃除で相続人の資格を失った者であっても、その子(被相続人の孫)には代襲相続権が発生します。
この代襲相続権に基づいて、遺留分が認められます。
ちなみに、相続放棄の場合には代襲相続権がないため、当然ながら孫に遺留分はありません。
■遺留分の割合
1.遺留分の割合はいたってシンプル
①直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合、1/3
②その他の場合、1/2
ポイントは①で登場する「のみ」の表現です。
つまり、これは「直系尊属のみ」が相続する場合を指しますので、配偶者と直系尊属が相続人になる場合は、遺留分は1/3ではなく1/2です。
2.ケーススタディ~遺留分の割合


Aの相続人はW(妻)、BCD(ともに子)である。
Aは死亡直前、Dに2000万円の贈与をしている。
Aが遺産なく死亡した。
3.解説~遺留分の割合
①まず法定相続分を確認します。
W=1/2
B=1/6(1/2×1/3)
C=1/6(1/2×1/3)
D=1/6(1/2×1/3)
②次に各人の遺留分を計算します。
ここでポイントとなるのが、Dです。
Dは子であるため、遺留分権利者です。
Dへの贈与が他の相続人の遺留分を侵害しているとはいえ、Dが遺留分権利者の資格を失うわけではありません。
Dは「遺留分権利者」だが「遺留分減殺請求権利者」ではない
という事です。
この場合の遺留分は「その他の場合1/2」となりますので、各相続人の遺留分は次の通り計算します。
W=1/4(1/2×1/2)
B=1/12(1/6×1/2)
C=1/12(1/6×1/2)
D=1/12(1/6×1/2)
※各人の法定相続分に遺留割合をかけている。
各人の遺留分の合計が6/12、つまり1/2になっていることを再確認して下さい。
③最後に生前贈与額に各遺留分をかけます。
W=2000×1/4=500万円
B=2000×1/12=166万円
C=2000×1/12=166万円
以上がWBCからDに対する遺留分減殺請求権の金額です。
■遺留分が侵害された場合
1.ケーススタディ~遺留分を侵害する遺言は無効か?


Aの相続人はBC(ともに子)である。
Aは遺言で、「自分の財産は全て○○市に寄付する」とした。
Aが死亡した。
2.解説~遺留分を侵害する遺言は無効か?
さてここで問題となるのは、
遺留分を侵害する遺言の有効性です。
遺言の無効原因には、「遺留分を侵害する場合」が挙げられていません。
つまり、遺留分を侵害する遺言、贈与もいったんは有効なのです。
3.遺留分の主張は遺留分減殺請求にて
自分の遺留分が一部であれ、全部であれ侵害されている。
その場合、相続人として取りうる手段は2つです。
①遺留分減殺請求を行う
(遺留分侵害を知ってから1年、相続開始から10年)
②何もしない
つまり、侵害されている遺留分を取り返すか否かは、相続人の自由なのです。
「遺留分減殺請求権を行使しない」という選択肢も取ることができます。
■遺留分を放棄することはできるか?
1.相続開始後の遺留分の放棄
相続開始後、遺留分を放棄するのは原則自由です。
自分の遺留分が侵害されている遺言や生前贈与があるのを知りつつ、それらを前提とした遺産分割協議を成立させる(署名押印)することで、実質的に遺留分を放棄することになります。
2.相続開始前の遺留分の放棄
これに対して、相続開始前(被相続人の死亡前)に遺留分を放棄することには様々な問題があります。
例えば、健在である被相続人や他の相続人らの圧力により、遺留分放棄を強いられる可能性があるからです。
そこで被相続人が健在である場合の「遺留分放棄」には家庭裁判所の許可が必要となっています。
蛇足ながら、「生前の相続放棄」はいかなる場合でも行うことができません。
3.遺留分放棄の効果
(相続放棄ではないことにご注意ください。)
相続人が複数ある場合、1人の相続人が遺留分を放棄した場合どうなるか。
遺留分の放棄は、他の相続人の遺留分に影響を与えるものではありません。
仮に相続人の1人の遺留分が1000万円とします。
遺留分を放棄したとしても、この1000万円の遺留分が、他の相続人に割り振られ、各人の遺留分(最低保証額)が増えるのではありません。
あくまでも、遺留分放棄は被相続人と個別相続人の関係にのみ影響するため、「遺留分放棄は被相続人の自由処分割合(遺言の自由度合い)を増やす」
事にとどまるのです。
■遺留分の対象は「基礎財産」
1.基礎財産の内訳
遺留分計算上の「相続財産」のことを「基礎財産」と呼びます。
遺産分割の場で使う「相続財産」とは異なる考え方ですので注意が必要です。
まず基礎財産の内訳を示します。
民法1029条
「相続開始時の財産」 + 「贈与財産」 - 「債務」
「特別寄与分」が一切考慮されていないことから、遺留分が特別寄与分に優先するわけです。
2.遺贈の取り扱い
遺贈(遺言による譲渡)は「相続開始時の財産」から支出するものですので、基礎財産に含まれることになります。
つまり、遺留分減殺請求の対象です。
3.贈与財産の取り扱い
もう一度「遺留分制度の本質」に立ち返ります。
遺留分制度は、私法の大原則である私的自治、所有権絶対の原則に対する制限です。
つまり、遺言や生前贈与でなされた本人(被相続人)の行為を、一定の範囲で制限する仕組みです。
しかし仮に全ての生前贈与が、本人の死亡後に制限を受ける(つまり遺留分減殺請求の対象)となると、法律関係が不安定になります。
生前贈与自体が、死後の遺留分減殺請求期限の経過(1年)まで、不確定となるという意味です。
そこで、民法では遺留分の対象となる贈与に「一定の範囲」を定めています。
民法1030条
「贈与は被相続人死亡前、1年内のものに限り遺留分の対象とする」
つまり、1年以上前になされた贈与は、いかに遺留分の保護が必要とはいえ、遺留分計算対象から外れるという趣旨です。
しかしこれには例外があります。
■1年以上前の贈与でも遺留分基礎財産に
1.遺留分権利者に損害を与えることを知った上での贈与
つまり、多額の生前贈与をすることで法定相続人に損害が出るという事を知った上での贈与は、1年以上前になされても、遺留分の対象(基礎財産)になるという趣旨です。
(民法1030条後段)
例えば家族(相続人)と別居し、不倫関係にある者への生前贈与などです。
この場合「損害が出ることを知った上で」とは、
①「加害目的・意図があるかどうか」は不問。「加害することになる事」を知っているだけで遺留分対象。
②「法律を知っている、または知らない」も不問。
③「遺留分権利者が誰かを知っている、または知らない」も不問。
つまり遺留分権利者の保護が手厚く考えられているわけです。
2.婚姻、養子縁組等の目的の贈与
相続人の婚姻、養子縁組のための贈与について、死亡の1年前以前になされた場合であっても、遺留分の対象(基礎財産)になります。
相続人間相互の公平を期すというのが趣旨です。
(最判昭51.3.18)
3.不当対価の行為
直接的には贈与に該当してなくても、取引の中に不当な対価(みなし贈与)が含まれているケースです。
例としては、相場よりも家賃を安く設定して貸す、相場よりも安い金額で不動産を売却するなどです。
このような場合、相場と実際の取引額の差が「みなし贈与」とされ、死亡の1年前以前になされた行為でも、遺留分の対象(基礎財産)になります。
これらの行為が、民法1030条(遺留分対象は1年以内の贈与に限る)の例外として機能し、相続人の遺留分を保護しているのです。
■遺留分の侵害が問題となるケース
1.遺言による遺留分の侵害
最も一般的なケースです。遺言により、被相続人が自分の財産を特定の相続人や外部の第三者に譲り渡すことを選択する事例です。
2.生前贈与
被相続人が生前に、自分の財産を特定の相続人や外部の第三者に譲り渡す事例です。
3.死因贈与
一方的な意思表示である遺言とは異なり、被相続人が生前に、自らの死亡を原因として、財産を特定の相続人や外部の第三者に譲り渡す事(死因贈与)を約束(契約)する事例です。
4.遺言による相続分の指定
法定相続分とは異なる相続分を遺言で指定する事例です。
5.相続人を受取人とする生命保険契約
被相続人が、相続人の1人を死亡生命保険契約の受取人指定している事例です。死亡生命保険契約は原則として相続財産になりませんが、例外的に相続財産とのバランスにより「相続財産を構成する」と認められるとき、遺留分が問題となります。
上記のケースで、遺留分の侵害が起こりえます。
■寄与分と遺留分が衝突したら?
1.ケーススタディ~寄与分と遺留分の衝突


Aには相続人BC(ともに子)がある
Aは個人商店を営んでいる
Bは他社に勤務しながら長年無償でAの事業に貢献し、給与を得ていない
Aが500万円を残して死亡した。
2.解説~寄与分と遺留分の衝突
Bの行為が「特別の寄与」として認められる場合、Bは遺産500万円から優先的に「寄与分」を受け取り、残額をBCの協議で分割することになります。
ここで問題となるのが、
Bの特別寄与分 > 遺産
となるようなケースです。
具体的には例えばBが、
「自分の寄与分を金銭に見積もると、700万円である」
と主張したとします。
これに対してCが
「自分には遺留分がある」
と反論するようなケースです。
■遺留分は寄与分に優先する
1.遺留分の対象財産
遺留分の計算対象となる財産は、民法1029条で定められています。
そこでは、民法904条の2のように、
「分割対象となる相続財産から寄与分を別枠で取り分ける」
という規定がありませんので、
相続人間で「遺留分(最低の権利)」と「寄与分(特別貢献分の権利)」がぶつかった場合、遺留分が優先されるわけです。
従って、Bにいくら700万円分の特別寄与があったとしても、Cの遺留分が優先して保護されます。
2.寄与分と遺留分が衝突した場合の計算方法
500万円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)
=125万円
結果
Bの相続分 375万円
Cの相続分 125万円
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】