介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑤|養子と非嫡出子の法定相続分

■養子と実子に法定相続分の差はあるのか?
1.養子縁組の仕組み
日本では20歳になったら自分より年下の人を養子にすることが出来ます。
年上を養子できるとすると、ややこしくてたまりませんね。
養子に対する法定相続分をご説明するためには、嫡出子(ちゃくしゅつし)の理解が必要です。
2.嫡出子とは何か?
嫡出子とは「妻が婚姻中に身ごもった子」を指します。(民法772条)
そしてその子は原則、夫の子と推定されます(同条)
また、養子については
民法809条「養子は養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」
ことになりますので、この2つの理屈を合わせると、
「実子も養子も法定相続分は同じ」
という結論に至ります。
■嫡出子と非嫡出子で法定相続分に差はあるのか?
1.非嫡出子とは何か?
非嫡出子を「嫡出子」とは逆の側面から説明すると次のようになります。
「妻が婚姻中に身ごもったのではない子」(772条)
また、
「婚姻届日から200日以内に生まれた子、離婚日から300日経過後に生まれた子」
も、いったんは非嫡出子と推定されます。
旧民法では、
「法律婚=秩序、守るべきもの」
との考えのもとで、
嫡出子:非嫡出子=2:1
という相続分でした。
2.ケーススタディ~非嫡出子の法定相続分


AB間に実子Cがある。
Aには別に非嫡出子Dがあり認知している。
Aが死亡した。
3.解説~非嫡出子の法定相続分
旧民法では、BCDの法定相続分はそれぞれ、
B=1/2
C=2/6(=1/3)
D=1/6
としていました。(旧民法900条4項)
しかし、社会情勢の変化を受けて平成25年、この状態を「違憲」とする画期的な判決が出されました。(最大決平25.9.4)
結果的に民法が改正され、
「嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じ」
となったわけです。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】





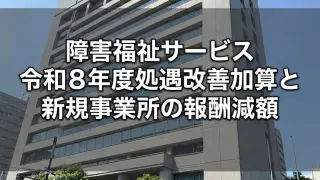


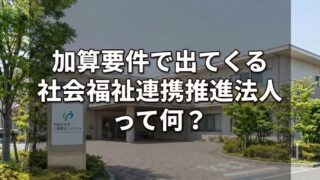


コラムサムネ02-320x180.jpg)



