訪問看護ステーションの運営規定の作り方、開業後の「やらなければならない事」、「やってはいけない事」

-1.jpg)
-1.jpg)
訪問看護の運営規定の作り方、事業開始後の注意点について解説します。運営規定の記載事項を詳しく理解していますか?また訪問看護事業を運営するにあたり、「やらなければならないこと」、「やってはいけないこと」を正確に理解していますか?このコラムの内容を理解せずに訪問看護の開業に臨むことは極めて危険です。
このコラムの推奨対象者
・訪問看護ステーションの運営規定を理解したい人
・訪問看護ステーションに課せられた責務を理解したい人
・その他設立・開業前に注意しなければならない点を理解したい人
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に特化した専門会社です。このコラムのリライト(更新)時、令和3年8月時点で、累積設立支援実績が400社を超えました。訪問看護事業の運営基準についても、日々の開業相談の中でご相談対応しておりますので、どうぞ安心してお読み下さい。
- 1. 訪問看護ステーションの運営規定に書くこと
- 1.1. 事業の目的および運営の方針
- 1.2. 従業者の職種、員数および職務の内容
- 1.3. 営業日、営業時間
- 1.3.1. 営業日、営業時間
- 1.3.2. サービス提供日、サービス提供時間
- 1.4. 指定訪問看護の内容、および利用料その他の費用の額
- 1.4.1. 指定訪問看護の内容
- 1.4.2. 訪問看護の利用料
- 1.5. 事業の実施地域
- 1.6. 緊急時における対応方法
- 2. 掲示義務(運営規定概要、勤務体制、重要事項説明書)
- 3. 訪問看護サービスの提供拒否と拒否時の対応
- 3.1. 訪問看護サービス提供の拒否
- 3.2. サービス提供を拒否した場合の対応
- 4. 受給者証の確認、要介護認定申請・更新の援助
- 5. サービス担当者会議への参加、居宅支援事業所との連携、利益提供の禁止
- 6. サービスの提供記録と訪問看護報告書
- 7. 保険適用外サービス
- 8. 同居家族への訪問看護サービス提供禁止
- 9. 訪問看護事業者から市町村への通報義務
- 10. このコラムのまとめ
・
訪問看護ステーションの運営規定に書くこと
訪問看護ステーションの指定申請書に添付が義務付けられる運営規定。ここでは訪問看護ステーションの運営規定について、必要記載項目を確認していきます。
事業の目的および運営の方針
御社の経営理念および訪問看護ステーションの運営方針について記載します。運営規定は利用者の目にする書類となるため、なるべく経営者の想いを分かりやすい表現で記載しましょう。
従業者の職種、員数および職務の内容
管理者、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に区分しつつ、それぞれ常勤、非常勤での人数を記載します。あくまでも事業開始時点の人数で問題ありません。
営業日、営業時間
ここでは次の定義に注意して記載しましょう。
営業日、営業時間
事務所のドアが開いている日、時間帯のことです。
サービス提供日、サービス提供時間
実際の訪問看護サービスを提供する日、時間帯のことです。24時間体制で電話対応が可能な場合は、その旨も記載します。
指定訪問看護の内容、および利用料その他の費用の額
指定訪問看護の内容
例示すると主に次のような内容となります。
「指定訪問看護の内容」記載例
・病状・障害の観察
・リハビリテーション
・ターミナルケア
・療養生活や介護方法の指導
・カテーテル等の管理
訪問看護の利用料
介護保険適用の場合は「報酬告示上の料金」と記載し、介護保険適用外の場合も、「法令基準に基づいて説明および徴収を行う」との趣旨で記載すれば問題ありません。
事業の実施地域
訪問看護ステーションから実際に出張訪問する地域を記載します。実施地域内での利用申し込みは、「訪問看護サービスの提供拒否と拒否時の対応」で示す場合を除いては断ることができません。
またここで記載する「事業の実施地域」についてはあくまでも目安であるため、実施地域を超えてサービスを行う事を妨げる趣旨ではないこと、またその場合には追加の交通費を請求することができることも理解しておきましょう。
緊急時における対応方法
訪問看護サービスの提供中に緊急事態が生じた場合は、主治医および管理者へ即座に報告して必要な措置を講じる旨、またそれらに連絡が取れない場合は緊急搬送の手配を取る旨を記載します。
掲示義務(運営規定概要、勤務体制、重要事項説明書)
次に訪問看護事業者が事業所(ステーション)内に掲示しなければならない書類について確認しましょう。
訪問看護事業者は、利用者、その家族または事業所で働く職員がいつでも閲覧できるよう、次の書類を掲示しておかなければなりません。
事業所への掲示書類
ア)運営規定の概要版
イ)看護師等の従業員の勤務体制
ウ)重要事項説明書
重要事項説明書とは、ア)、イ)に加えて事故発生時の対応、苦情処理体制等、利用者がサービス選択するために必要な事項を記した書面のことを指します。
訪問看護サービスの提供拒否と拒否時の対応
訪問看護サービス提供の拒否
ここでは運営規定に記した訪問看護サービスについて、利用申し込みを拒否できるかどうかを確認します。
介護保険(医療保険)サービスは、収益の大半が公費によって賄われる公的サービスです。さらに訪問看護サービスは利用者の生命と健康に関わる、極めて重大な任務を担います。
そのため、訪問看護ステーションに利用申し込みがあった場合、事業所側に正当な理由がない限り拒否することができません。
ここで言う正当な理由とは次の3例です。
サービス提供を拒否できる正当な理由
・当訪問看護ステーションの人員不足のため対処できない
・利用申し込み者の居宅が、当訪問看護ステーションの実施地域外
・技術上の問題等で適切な訪問看護サービスを提供することができない
サービス提供を拒否した場合の対応
訪問看護ステーションが上記の理由で、サービス提供を拒否する場合、利用者保護のため、断ったステーション側に次の責任が生じます。
サービス提供を拒否した場合の責任
・主治の医師および居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)へ連絡する
・適切な他の訪問看護ステーションを紹介する
このような場合に備えて、地域の同業者(訪問看護)とは良好な関係性を構築することも重要となります。
受給者証の確認、要介護認定申請・更新の援助
訪問看護ステーションがサービス利用の申し込みを受けた場合、次の対応義務があります。
サービス利用申込時の対応義務
1.被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無と有効期間を確認する
2.要介護認定の申請を行っていない利用者の場合、申請を援助する
3.要介護認定の有効期間満了が近い場合、更新手続きを援助する
要介護認定の更新は、申請から最大で30日かかるため、少なくとも有効期間の30日前には更新申請する必要がある点を理解しておきましょう。
サービス担当者会議への参加、居宅支援事業所との連携、利益提供の禁止
利用者が利用する介護保険サービスについて、計画を立てるのが居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)です。
訪問看護ステーションの看護師は、居宅介護支援事業者が主催するサービス担当者会議に参加することで、利用者の心身の状態について、医療福祉全般の関係者と情報を共有する責任を負っています。
特に居宅介護支援事業者とは、ケアプランと実際に提供する看護サービスの整合性を確認する目的で、連携を密にしなければなりません。
一方で、訪問看護ステーションを含む、全ての介護サービス提供事業者は、居宅介護支援事業者に対してあらゆる利益供与が禁止されている点にも注意しましょう。
サービスの提供記録と訪問看護報告書
訪問看護事業者は、サービスの提供(訪問)の都度、提供した具体的なサービス内容を記録(サービス提供記録)しなければなりません。
この訪問看護サービス提供記録に基づき、定期的に主治医に提出するのが訪問看護報告書です。
訪問看護報告書には、訪問日を明らかにしたうえで、訪問看護サービス提供記録に基づき、次の事項を記載します。
訪問看護報告書への記載事項
・病状の経過
・看護、リハビリテーションの内容
・家庭での介護の状況
・その他特記事項
保険適用外サービス
訪問看護サービス提供に関係して、保険外のサービスを提供することについて検討してみましょう。
保険外のサービスとは例えば次のようなサービスです。
保険外サービスの例
・家事代行サービス
・理美容サービス
・マッサージ
主目的はあくまでも訪問看護であるため、上記のような保険外サービス提供の糸口として訪問看護を実施することは法令で厳しく禁止されています。
保険外サービスを提供する場合には、それが保険対象外である旨、および利用料について利用者および利用者の家族に詳しく説明する必要があります。
同居家族への訪問看護サービス提供禁止
家族には相互に扶助の義務があるため、看護師自らが同居の家族に対して訪問看護サービスを提供した場合、保険算定することはできません。
一方で、同一の訪問看護ステーションに所属する他の看護師であれば、上記の訪問看護サービスを提供することができるため、勤務体制の計画次第では希望が叶う可能性があります。
訪問看護事業者から市町村への通報義務
訪問看護ステーションにおいては、利用者が次に該当する場合、利用者の居住する市町村に通知する義務があります。
訪問看護ステーションから市町村への通知義務
・理由なく訪問看護師の指示に従わないことで、要介護度を悪化させる場合
・不正手段によって保険給付を受けようとする場合
公費の不正流用について、訪問看護ステーションも監視の一翼を担っていることを理解しましょう。
このコラムのまとめ
以上が訪問看護ステーションの設立・開業前に把握しておくべき運営上の注意点です。当社に訪問看護ステーションの設立・開業をご依頼の方には、運営規定の作成も当然に含めて対応しているので、どうぞご安心下さい。
設立前の多忙な時期に、事務作業によって時間を取られないためにも、計画段階から当事務所へご相談されることをお勧めします。
5万円で会社設立&指定申請
訪問看護事業 会社設立オールインワンパッケージは、会社設立、指定申請ほか、訪問看護の立ち上げ、開業に必要となる全ての法手続きをパッケージにしたサービスです。詳細は左の画像をクリックしてご確認ください。
・
訪問看護を開業されたお客様の声《えむ訪問看護ステーション様》
訪問看護のリハ職報酬減額 令和3年度介護報酬改定
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538



-300x224.jpg)
-300x114.png)

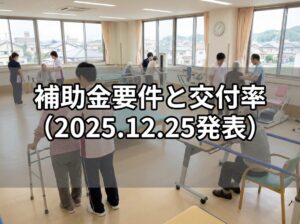









の作成義務と作成単位|介護事業所・障害福祉事業所におけるBCP作成のプロセス-300x149.png)


とは?コラムサムネ01-300x135.png)

はいくら必要?必要総額と自己資金の差額部分を公庫融資で補うコラムサムネイル-300x150.png)










・児童発達支援管理責任者(児発管)とは?-300x200.jpg)
コラムサムネ02-320x180.jpg)
-コピー-320x180.jpg)
|人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練コラムサムネ-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
